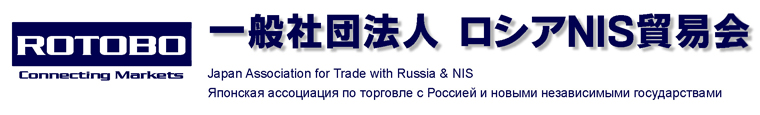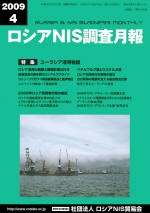���V�ANIS��������2009�N�S�������W�����[���V�A�`�p���� |
|
���W�����[���V�A�`�p���� |
|
Introduction
|
���V�A�`�p�̊T�v�Ɛ����v��̍s�� |
�������|�[�g
|
�y�e���u���O�`�ƃE�X�`���K�` �\���V�A�E�R���e�i�A���̋��_�\ |
�������|�[�g
|
���C�`�p�̔e���������V�A�ƃE�N���C�i�i��j |
�������|�[�g
|
���V�A���C�n����v�`�̊T�� |
�������|�[�g
|
���j�m�E�\���K���j�A���Y�Ƌ��_�ƌo�ϓ��� |
�r�W�l�X�őO��
|
�����f�Ղ̔��W���x���鑍��������� |
�u���^
|
�����}���X�N�A���n�u���v�� |
�f�[�^�o���N
|
�����Ō��郆�[���V�A�̍`�p |
|
�������|�[�g
|
2008�N���V�A��p�Ԏs��̑���
�\���Z��@�̉e���𒆐S�Ɂ\ |
�f�[�^�o���N
|
2008�N�̃��V�A�̃��[�J�[�ʓS�|���Y |
�f�[�^�o���N
|
���V�A�̐헪�d�v���295�Ѓ��X�g |
���[���V�A����
|
�E�Y�x�L�X�^���̓d�@��������ɂ����铊���@�� �\�C�Y�o�T���t�E�E�Y�x�L�X�^���d�@��Ƌ����u���\ |
������������
|
�悤�₭���������T�n�����Y�V�R�K�X�̗A�� |
�h�[���E�N�j�[�M
|
N.�i�U���o�G�t���w���a�ƒ��a�̐���x |
�N���������E�E�H�b�`
|
�v�[�`���̋~������ |
�G�l���M�[�Y�Ƃ̘b��
|
���}�������̃K�X�z���J���� |
�����ԎY�Ǝ��]
|
2008�N�̃��V�A�̃g���b�N���Y�E�̔��� |
���V�A�r�W�l�XQ&A
|
�����V�A�̈�Ë@��r�W�l�X |
�ƊE�g�s�b�N�X
|
2009�N�Q���̓��� �����[�����T�N�������X�N���ŐV���J�X�� 2009�N�P���̗A�o���ʊ֎��� |
���V�A�`�p�̊T�v�Ɛ����v��̍s��
�@����̍����ł́A���V�A�ENIS�����̍`�p����W����B�`�������邱�̋L���ł͂܂��A�ŏd�v���ł��郍�V�A�̍`�p�ɂ��A���_�I�ɘ_���邱�Ƃɂ���B
�@���V�A�͍L��ȗ��n�������߁A�S����p�C�v���C���ȂǗ�����i�����ڂ��ꂪ�������A�`�p������ɗ��ʏd�v�ȗA�����_�ł���B�Ƃ��ɊC�m���ł�����{�ɂƂ��ẮA���V�A�Ƃ̖f�Ղ��s����ō`�p�͂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����݂ł���B
�@2008�N�A���V�A�ł́u2030�N�܂ł̗A���헪�v�ƘA�M���ʃv���O�����u2010�`2015�N�̗A���V�X�e���̔��W�v�����F����A�����ł́A����߂Ĉӗ~�I�ȍ`�p�������\�肳��Ă���B�ȉ��ł́A���V�A�ɂ����邱��܂ł̍`�p��������̓��e�Ǝ��т��T�ς��A��L�̂Q�����𒆐S�ɍ���̌v������Љ�邱�ƂƂ������B
�@�y�e���u���O�`�ƃE�X�`���K�`
�\���V�A�E�R���e�i�A���̋��_�\
���V�ANIS�o�ό����� ������
�����F��
�͂��߂�
�P�D�T���N�g�y�e���u���O�`�̊T�v�ƌ���
�Q�D���V�A�ő�̃R���e�i�戵�`
�R�D�V�`�u�A���@���|�[�g�v�̌��v��
�S�D���X�Ɖғ����n�߂�E�X�`���K�`
������
�͂��߂�
�@���݁A�T���N�g�y�e���u���O�ɂ͓��{�̃g���^�A���Y�A�X�Y�L�̂ق��AGM�A����Ȃǐ��E�̎����ԃ��[�J�[���������Ői�o���A���n���Y���J�n���悤�Ƃ��Ă���i�g���^�AGM�͂��łɐ��Y���J�n�j�B
�@���̂����̎����ԃ��[�J�[�͍H�ꌚ�ݒn�Ƃ��ăT���N�g�y�e���u���O��I�������̂ł��낤���B�����n�ւ̋߂��A�s�s���{�ɂ��C���Z���e�B�u�A�J���͂̊m�ۂȂǗl�X�ȗ��R���l�����邪�A����ɗ��ʏd�v�ȏ����Ƃ��č`�̑��݂����������Ƃ͂ł��Ȃ��B����A�e���[�J�[�̎����ԍH�ꂪ�{�i�I�ɉғ����n�߂�ƁA���i�A�����ō`�̏d�v���͂���ɍ��܂�ł��낤�B
�@�{�e�ł́A����܂��܂��ݕ��ʂ̑��傪�\�������T���N�g�y�e���u���O�`�̊T�v�Ɠ��`�̑�֍`�Ƃ��Ċ��҂����E�X�`���K�`�̌��v��ɂ��āA�Ƃ��ɃR���e�i�^�[�~�i���̌���ƌ��ʂ��𒆐S�ɂ��Љ�邱�ƂƂ������B
�@���C�`�p�̔e���������V�A�ƃE�N���C�i�i��j
���V�ANIS�o�ό����� ����
�����ϑ�
�͂��߂�
�@���C�E�A�]�t�C�́A�V�����Ɉ͂܂ꂽ���j�[�N�ȓ��C�ł���B���ݏ����������o�ϐ����𐋂��A����ɔ����`�p�̐������}��������A���n�Ȑ����E�o�ϑ̐��䂦�̍����������A�`�p�Z�N�^�[�̓_�C�i�~�b�N�����ׂƂ����l����悵�Ă���B
�@���V�A�ƃE�N���C�i�̗����ɂƂ��Ă��A���C�̏d�v���͘_��҂��Ȃ��B���V�A�ő�̍`�p�ł���m���H���V�[�X�N�`�́A���C���݂Ɉʒu����B�E�N���C�i�Ɏ����ẮA�C�`�����ׂč��C�E�A�]�t�C�ɖʂ��Ă���B
�@�}�P�́A���V�A�̍��C���`�ƃE�N���C�i�̏��`�ɂ��2007�N�̎戵�ݕ��ʂ��r�������̂ł���B�����[�����ƂɁA���V�A�̉ݕ��ʂ��P��5,972�����A�E�N���C�i�̉ݕ��ʂ��P��5,792�����ŁA�قڌ݊p�ł���B���V�A���m���H���V�[�X�N�`�ɏW�����Ă���̂ɑ��A�E�N���C�i�͒����K�͂̍`�ɕ��U���Ă���Ƃ����Ⴂ�͂���ɂ���A�g�[�^���Ō���Η����͂܂��Ɂu�D�G��v�ƌ����Ă����B
�@�����P�ɋK�͂������Ƃ��������ł͂Ȃ��B�����͉ݕ��̒D�������Ƃ����Ӗ��ł��A���C�o���W�ɂ���B���V�A�E�E�N���C�i�̐��{����ыƊE�ɂ��`�p�J���\�z�E�v��́A���݂��������ӎ��������̂ƂȂ��Ă���B���V�A���ɂƂ��ẮA����̍`�p���g�[���A���݃E�N���C�i�̍`�ŏ�������Ă��鎩���ݕ���D�҂��邱�Ƃ��A�����I�ȉۑ�̂ЂƂ��B���V�A�̓E�N���C�i�ƑΗ����邱�Ƃ������Ƒ������߁A����͈��S�ۏ��̗v���ł�����B�t�ɁA�E�N���C�i���ɂ́A���V�A�ݕ��̃g�����W�b�g��������ێ����A����ɂ͍��C�ɂ�����R���e�i�A���̃l�b�g���[�N�Ŏ哱�I�Ȓn�ʂ�z�������Ƃ����v�f������B
�@�{�e�ł́A���V�A�ƃE�N���C�i�̍��C�`�p�̏������A�����̑R�W���ЂƂ̎��ɁA�_���邱�ƂƂ���B�Ȃ��A�����̓s����A�㉺�ɕ����A�܂�����̓��V�A�Ɋւ����P�߂����͂�����B�E�N���C�i��������Q�߂́A�T�����܂��͂U�����Ɍf�ڂ���\��ł���B
�@���V�A���C�n����v�`�̊T��
���V�ANIS�o�ό������@������
�V�����
�͂��߂�
�P�D�i�z�g�J�`
�Q�D���H�X�g�[�`�k�B�`
�R�D�E���W�I�X�g�N�`
�S�D���̑��̍`
�Ō��
�͂��߂�
�@���V�A�ɓ����`�̏d�v�������܂��Ă���B�o�ϐ����ɔ��������̊������ŁA�������N�A�ݕ��戵�ʂ�L���Ă����B���̈���ŁA�ɓ����`���x�z���郂�X�N�����{�́u�v���C�x�[�g�|�[�g�v���͈�i�Ɛi�݁A�����I�ȉד����͎�������Ă��Ȃ��B���Z��@�ɂ��i�C�̋}���Ȉ����ŁA�ɓ��̍`�̏���ς����B�����Ŗ{�e�ł́A���V�A�ɓ��̒��ł��戵�ʂ̑����`�p���W�����鉈�C�n����v�`�̊T������у��X�N�����{�ɂ��`�p�x�z�̖��_�ɂ��čŐV���������ĕ���B
���j�m�E�\���K���j�A���Y�Ƌ��_�ƌo�ϓ���
���V�A�Ȋw�A�J�f�~�[�ɓ��x���o�ό�����
�n.�����W��
�͂��߂�
�P�D���j�m�`�ƃ\���K���j�`
�Q�D�A���Y�Ƌ��_�̊J���v��
�R�D�`�p�o�ϓ���̑n��
�S�D�ɓ��n��J���̉ۑ�ƓW�]
�͂��߂�
�@���V�A�ɓ��̒����J���헪�́A���n��ɂ������K�͂ȗA���Y�ƕ����V�X�e���̌`����O��Ƃ��Ă���B���̈�Ƃ��āA�n�o���t�X�N�n���ɂ����ă��j�m�E�\���B�G�c�J���K���j�i�ȉ��A�\���K���j�j�A���Y�Ƌ��_���`���������B���̃v���W�F�N�g�̍ł��d�v�ȗv�f�́A�ɓ��n�揉�́i�����Č����_�ł͊C�`�Ƃ��ă��V�A�B��́j�`�p�o�ϓ��悪�n�݂����Ƃ����_���B
�@�`�p����ł́A�`�p�{�݂̋ߑ㉻�Ɛ����A�S���E�����ԗA���A�G�l���M�[�A�����T�[�r�X�A�Љ�C���t���̊g�[���}����B�����ɁA��A�̎Y�Ǝ{�݂����݂����v�悾�B���Ƃ��A�D���C���E���D�Z���^�[�A�؍ނ⋛�E���Y���̉��H�{�ݓ��̌��݂��v�悳��Ă���B
�@���̂悤�ȗA���Y�Ƌ��_�̌`���̊�ՂƂȂ�̂��A�\�A���ォ�瑶�݂��郏�j�m�`�ƃ\���K���j�`�̎��ӂɏW�ς���A���E�Y�Ǝ{�݂ł���B
�r�W�l�X�őO��
�����f�Ղ̔��W���x���鑍���������
���{�X�D�i���j
���X�N�����������@������Y����
�T���N�g�y�e���u���O���������@����ȌႳ��
�͂��߂�
�@���{�X�D��2004�N�A���X�N���ɑS�z�o���̎q��ЁuNYK���W�X�e�B�N�XCIS�v��ݗ����Ĉȍ~�A���V�A�����̍��ە����Ɩ��ɉ����A���V�A�����ł̍��i���ȕ����T�[�r�X����Ă��܂��B���݂̓��X�N���ƃT���N�g�y�e���u���O�Ɏ��������\���A���X�N���ɐV�q�ɂ�����������ȂǁA���B�n��ł̎��Ƃ��L����Ɠ����ɁA�T�n�����ł̓��V�A���p�[�g�i�[�Ƌ��͂��āA�T�n�����U��LNG�D���A�q�����܂����B�����ł́A���X�N���ƃT���N�g�y�e���u���O���������̏����ɁA���V�A�̕����Ԃ𒅁X�Ɛ���������{�X�D�̃r�W�l�X�̌���ɂ��Ďf���܂��B
�u���^
�����}���X�N�A���n�u���v��
�u���V�A�ɂ�����^�A�C���t���v���W�F�N�g�Z�~�i�[�v���@�i2009�N�P��14���A�@����فj
�}�l�[�W�����g��Ёu�����}���X�N�E�g�����X�|�[�g�E�Z���^�[�v
���@�`�D�V���|���@�������c
�@2009�N1��14���ɁA�����E�@����قɂāA�����B�`���E���V�A�^�A��b��s�����}�����A���y��ʏȎ�ÁA���V�ANIS�f�Չ�̌㉇�ɂ��u���V�A�ɂ�����^�A�C���t���v���W�F�N�g�Z�~�i�[�v���J�Â���܂����B�����ł́A���V�A���ɂ���A�̂̕Ȃ�����A�����̓��W�e�[�}�̍`�p�ɐ[���֘A����v���[���e�[�V�����u�����}���X�N�A���n�u���v��v�̗v�|�����Љ�����܂��B���s�����̂́A���o�ϑ�b�ŁA���u�����}���X�N�E�g�����X�|�[�g�E�Z���^�[�v�В��̂`�D�V���|���@�������c���ł��B
�@�Ȃ��A�V���|���@�������c���̓p���[�|�C���g�̎��������p���v���[���e�[�V�������s���Ă��܂����A�{�L���ł͎����̓s����A�����͏ȗ������Ă��������܂��B������̃T�C�g���A�p���[�|�C���g���A�b�v���Ă���܂��̂ŁA�����p���������B
2008�N���V�A��p�Ԏs��̑���
�\���Z��@�̉e���𒆐S�Ɂ\
���V�ANIS�o�ό������@����
�����
�͂��߂�
�P�D���Y����
�Q�D�̔�����
�R�D�o�ϊ�@��̍��Y���[�J�[�̏�
�S�D�o�ϊ�@��̊O���n��Ƃ̓���
�T�D�o�ϊ�@��̃f�B�[���[�̓���
������
�͂��߂�
�@���V�A�̏�p�Ԏs���2008�N�ɓ����Ă���������ɐ������Ă����B�Ƃ��ɊO���V�Ԃ̔̔����D���ŁA2008�N�P���̔̔��䐔�͑O�N�������53�����̐L�т��������B���̌���̔��̍D�����͑����A�㔼���̊O���V�Ԃ̔̔��䐔�͑O�N������47�����̖�106����ɒB�����B
�@�s��W�҂̑����́A�����������l�̏������Ɨ\�z���Ă����B�������A�W���ɂȂ�A�ω��̒����������n�߂��B�O�N������Ŕ̔��䐔���������ރ��[�J�[���ڗ����n�߁A�S�̂Ƃ��Ă��O�N������23���̐L�тɂƂǂ܂����B���̍�����A�s�ꂪ���n�����Ă��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ̐����s��̈ꕔ�Ś�����n�߂Ă����B
�@���̂悤�ȏ̒��A2008�N�X�����ɐ��E�I���Z��@���u������B�X�������O���V�Ԃ̔̔��䐔�͂���قǗ������܂Ȃ��������A10���ȍ~�̔�������n�߁A11���A12���ƂQ�����A���ŊO���V�Ԃ̔̔��䐔�͑O�N��������ƂȂ����B����A�����Y�Ԃ̔̔����č����������n�߁A�قƂ�ǂ̏����Y���[�J�[���ߏ�ɂ�����A���݊�@�I�ȏɒ��ʂ��Ă���B�܂��A�O���n��Ƃ̌��n�H����߂�����A���Z��@�ȍ~�A�S�ʓI�Ɉ������Ă���B
�@�ȏ�̏܂��A�{�e�ł́A���Z��@���^�����e���ɗ��ӂ��A2008�N�̃��V�A��p�Ԏs��̑��������݂�B����ɁA���Z��@�u����̏����Y���[�J�[��O���n��Ƃ̌��n�H��̌���ɂ��Ă��_����B
�@�f�[�^�o���N
���V�A�̐헪�d�v���295�Ѓ��X�g
�͂��߂�
�@���V�A���{�͍�N12��25���A���V�A�o�ς̍����𐬂��헪�d�v���295�Ђ̃��X�g�𐧒肵���B�ȉ��ɁA���̃��X�g���f�ڂ���i�w���V�ANIS�o�ϑ���x�Q��15�����ŏЉ�ς݂����A�v���̂ق��ǎ҂���̊S�����������̂ŁA�{�w����x�ɂ��Ę^���鎟��ł���j�B
�@���̃��X�g�ł��邪�A�v�[�`���̊̂���ŁA�V�����@���t��ꕛ�����S�ƂȂ���܂Ƃ߂��ƌ����Ă���B���X�g�̐���ɓ������ẮA�e��Ƃ̏]�ƈ����A�N���K�͂Ȃǂ��I���ƂȂ����悤���B�����A���̃��X�g�͕K�������ŏI�m��łƂ����킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ă���A���㐏����[�����Ƃ�������������B
�@156��178���d�����Ă��邵�A�q��Ђ��t�L����Ă���ȂǁA���m�Ɍ�����295�Ђł͂Ȃ��B�Ǝ�͂��Ȃ蕝�L�����A���Z�@�ւ͓����Ă��炸�A�܂��O���n��Ƃ��ΏۊO�ƂȂ��Ă���͗l�ł���B�V�F�����`�F���H��`�������ăh���W�F�h���H��`���Ȃ��ȂǁA�s���ȓ_���U�������B
�@���̃��X�g�Ɍf�ڂ���邱�ƂŁA��̓I�ɂǂ̂悤�ȃ����b�g������̂��́A���m�ɂȂ��Ă��Ȃ��i�����́u�N���������E�E�H�b�`�v�ł́A����ɍڂ�������Ƃ����č��̎x�������킯�ł͂Ȃ��Ǝw�E����Ă���A���ۂ��̂Ƃ���ł��낤�j�B�����A���V�A���{�ɂ��헪�I�d�v��ƂƔF�肳���Ӗ��͏������Ȃ��͂��ŁA���ڂɒl���鎑���ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B
���[���V�A����
�E�Y�x�L�X�^���̓d�@��������ɂ����铊���@��
�\�C�Y�o�T���t�E�E�Y�x�L�X�^���d�@��Ƌ����̍u�����\
�͂��߂�
�@�P��24�`29����A.�C�Y�o�T���t�E�E�Y�x�L�X�^�����a���d�@��Ƌ������������ꂽ�̂��@�ɁA���V�ANIS�f�Չ�ł͂P��27���A�����c���ɂ����āA�u�E�Y�x�L�X�^�����a���̓d�@�Y�Ɓv�Ƒ肷��v���[���e�[�V�������J�Â������܂����B�ȉ��ɁA���̃v���[���e�[�V�����̊T�v�����Љ�����܂��B
�@�Ȃ��A����E�F�u�T�C�g�ɁA�v���[���e�[�V�����������f�ڂ������܂����̂��A���킹�Ă����p���������B�i�ҏW���j
�N���������E�E�H�b�`
�v�[�`���̋~������
�@�T�n����LNG�H��̊��H���̋@��ɖ����ƃ��h���F�[�W�F�t�哝�̂̉�k���s���܂����B���{�͗̓y�����i�W�̓W�]���o�Ă����Ƃ������͋C��U��܂��܂����B��̓I�Ȏ����W�����m�łȂ��͖̂��x�̂��ƂŁA������W�҂̎���PR�����Ȃ̂��Ǝv������A�ǂ����{�C�炵���̂ł��B
�@���{���{���J��Ԃ����V�A�ɐ\������ė����v�[�`���̖K�����T���Ɏ�������Ƃ����̂ŁA�W�҂͋������Ă���悤�ł��B�v�[�`���͖k���̓y�ԊҖ��Ɋւ��ď����Ă������Ă���Ƃ����b�̂悤�ł��B��������������͂��ł����A���̓_�͂܂��閧�Ȃ̂ł��傤�B
�@�哝�̂Ƃ���2005�N11���ɖK�������ۂɃv�[�`���́A���V�A�ɂ��S���̗L�͍��ۖ@��A�����I�ɂ��`����������ł���A���{�Ƃ̊ԂłȂ��̍��ӕ��������ԕK�v���A���V�A�Ƃ��Ă͂܂������Ȃ��A�Ɠ��{���ɓ`���܂����B���a���������̌p���ɂ͓��ӂ��邵�A���̕Ԋ҂ɂ��Ă�56�N�����錾�̃��V�A�����߂̐��łȂ�܂݂��c���Ƃ����p���������Ǝv���܂����A�S���̗L�ɉ��̒lj��������K�v�Ȃ��Ƃ����u�@���_�v�́A����ȑO�̃��V�A���{�̗��ꂩ��傫����ނ��Ă��܂��B�Ȃ������̐l�����������Ă��邽�߂ɓ��{�ɂ���Ă���Ƃ����̂ł��B
�@�������{���ɖk���̓y���Ői�W������A��Ԋ�Ԃ̂͂��Ԃ��ł��傤�B�z���C�g�n�E�X�ɌĂꂽ����x�����͈���ɉ��P�����A���͂Ⓘ�v�K���Ƃ����Ă��鐭������C�ɐ����Ԃ邩������Ȃ��̂ł�����B����̓v�[�`������~�����ւ𓊂��Ă��炤�悤�Ȃ��̂ł��B
�@�O���̔閧�͓��ǂɔC���āA�����ł́A�v�[�`��������ŋ߂̏��ώ@���Ă݂܂��傤�B�i���oi�j
�G�l���M�[�Y�Ƃ̘b��
���}�������̃K�X�z���J����
�@���V�A�͐��E�ő�̓V�R�K�X�����ʂ��ւ鍑�ł����A����܂Ŗ{�R�[�i�[�ł����x���G��Ă����Ƃ���A���̐��Y��Ղ͔Ƃ͌����������̂�����ł��B����́A���������ϓ_����傫�ȏœ_�ƂȂ郄�}�������ł̃K�X�z���J���ɂ��Ă��Љ�����܂��B
�����ԎY�Ǝ��]
2008�N�̃��V�A�̃g���b�N���Y�E�̔���
�@2006�N��2007�N�͌��݃u�[����_�ƕ���ł̓����̊������Ƃ������D�ޗ����d�Ȃ�A���V�A�̃g���b�N�̐��Y�Ȃ�тɔ̔��䐔�͑啝�ɐL�т܂����B2008�N���㔼���͍D���ł������A�X���̐��E�I���Z��@�ȍ~�͎��v���ɒ[�ɗ������݁A�ʔN�̐��Y�䐔�͑O�N��11������25��7,516��ɂƂǂ܂��Ă��܂��B
�@����́A�H�ȍ~�̏ɗ͓_��u���A2008�N�̎�v�����Y�g���b�N���[�J�[�ʂ̐��Y�E�̔��A�Ȃ�тɁA�O���u�����h�Ԃ̌��n���Y�̏����Љ�����܂��B
���V�A�r�W�l�XQ&A
���V�A�̈�Ë@��r�W�l�X
�@���h�x�[�W�F�t�哝�̂ƃv�[�`���͍��������̌����ڎw�����߁A����A�ی��A�Z��A�_�Ƃ̂S�̕�������ƗD��v���W�F�N�g�ɒ�ߋ��͂ɐ����i�߂Ă��܂����B���ɕی�����͑��̃v���W�F�N�g�����\�Z�K�͂��傫���A�O���̈�Ë@�탁�[�J�[�ɂƂ��ă��V�A�𖣗͓I�Ȏs��ɂ��Ă��܂��B�o�ϊ�@�̍Œ��ɂ����Ă��A�v���W�F�N�g���p�����Ď��{�����\���������ƌ����Ă��܂��B
�@����̓��V�A�̈�Ë@��s��ɂ��Ă̎���ɓ������܂��B