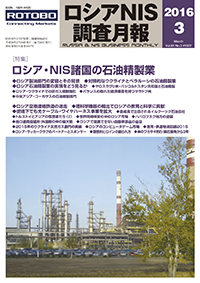 |
|
���V�ANIS��������2016�N�R�������W�����V�A�ENIS������ |
|
���W�����V�A�ENIS�����̐Ζ������� |
|
�������|�[�g |
���V�A��������̕ϗe�Ƃ��̔w�i |
�������|�[�g |
�ΏƓI�ȃE�N���C�i�ƃx�����[�V�̐Ζ������� |
�L�[�p�[�\���ɐu�� |
���V�A�Ζ������Ƃ̎�����ǂ����邩 |
�~�j�E���|�[�g |
�����X�������B�E�o�V�R���g�X�^�����a���ƐΖ����� |
�����ԎY�Ǝ��] |
���V�A�E�E�N���C�i�ł̔r�K�X�K������ |
�n��N���[�Y�A�b�v |
�o�����X�̎�ꂽ�o�ύ\�������T���g�t�B |
�����A�W�A���o�U�[�� |
�����A�W�A�E�R�[�J�T�X�̐Ζ��������� |
�������|�[�g |
���V�A��`�A���S���̖��� |
�r�W�l�X�őO�� |
���Ȋw�@��̗A�o�Ń��V�A�̋���ƉȊw�ɍv�� |
�r�W�l�X�őO�� |
�t�����ł����P�[�u���E���C���n�[�l�X���Ƃ��g�� |
�~�j�E���|�[�g |
�}�����Œ��ڂ����C���N�[�c�N�Ζ���� |
�����������z |
�g���X�g�C�ƃA�W�A�̎v�z�Ƃ����i�Q�j �\����1�����O�K���f�B�[�ɑ������莆�\ |
INSIDE RUSSIA |
���E���������̒��̃��V�A�s�� |
���V�A�ɓ����j�� |
�n�o���t�X�N�n���̋t�P |
���X�N���ւ� |
�ƃ��ʏ���c���F�O�����̒��̍ő吨�� |
�Y�ƁE�Z�p�g�����h |
���V�A�Ō����ł��Ȃ������ԕ��i�̕i�� |
�E�N���C�i�������_ |
2015�N�̃E�N���C�i�V�R�K�X����̎��� |
�f�W�^��IT���{ |
���V�A�̃R���s���[�^�Q�[���s�� |
���W�X�e�B�N�X�E�i�r |
�`�p�E�S���������2015 |
�R�������ܘb |
���V�A�E�T�b�J�[�N���u�̃p�[�g�i�[�ƃX�|���T�[ |
�V�l�}����ב��I�I |
���z�I�q���C���̑n���� |
�ƊE�g�s�b�N�X |
2016�N�P���̓��� |
�ʊ֓��v |
2015�N�P�`12���̗A�o���ʊ֎��сi����l�j |
�L�҂́u��ʑI���v |
�_�̃��J�T�M�ނ�F覐Δ�������R�N |
���V�A��������̕ϗe�Ƃ��̔w�i
���V�ANIS�o�ό������@����������
�����
�@2000�N��ɓ��胍�V�A�̐Ζ����Y�ʂ͋}���ɑ������n�߁A2005�N�̐��Y������2000�N�̖�1.5�{�ɒB�����B�����āA����Ɣ�Ⴕ�Đ�������̌��������ʂ��������n�߂��B2005�`2006�N���납��Ζ��̐��Y�ʂ̐L�т̕��͓݉����n�߂����A��������̌��������ʂ̑����e���|�͂ނ��������2005�N���_�Ŗ�Q��700�������������̂�2014�N�ɂ͖�Q��8,900�����ɒB�����B�����A2015�N�ɓ����Ă���ω��������n�߂Ă���A���N�̌��������ʂ͂Q�����x�Ƃ����킸���ł͂��邪�O�N����������B���V�A�̐�������̌��������ʂ��O�N�̐����������͎̂��ɏ\���N�Ԃ�̂��Ƃł������B
�@�܂��A���V�A�̐�������ł�2011�N���납��ϋɓI�ɐݔ��̋ߑ㉻�������i�߂��Ă������A��͂�2015�N�ɂȂ��Ă��炻�̐i���ɉA�肪�����n�߂Ă���B���ɁA���V�A�ő�̐Ζ���Ђł��郍�X�l�t�`�P���̐������̋ߑ㉻�̒x�ꂪ�ڗ����Ă���A���̂��Ƃ������̂ЂƂƂȂ�A�K�\�����̐V��������ւ̈ڍs�����N�x��邱�ƂƂȂ����B
�@�{�e�ł́A2015�N�ɓ���ώ@����n�߂������̕ω��̔w��ɂ��鎖��ɗ��ӂ��A�Ζ����i�̐��Y�y�їA�o�A�ߑ㉻��A����ւ̓������ɒ��ڂ��Ȃ���A���V�A�̐�������̌�����Љ��B
�ΏƓI�ȃE�N���C�i�ƃx�����[�V�̐Ζ�������
���V�ANIS�o�ό������@��������
�����ϑ�
�@���\�A�����̂����A��NIS�����ɑ����E�N���C�i�ƃx�����[�V�́A�o�ϔ��W�̏������������ʂ��Ă���ƌ�����B�Љ��`����ɁA��Ƀ��V�A���猴�R���B���A����𗘗p�������H�Y�ƂW�����A���H�i�̋����n�Ƃ��Ă̖�����S�����B
�@���̂��Ƃ́A�Ζ������Ƃɂ����Ă͂܂�B�E�N���C�i�ƃx�����[�V�͓Ɨ��ɍۂ��āA���V�A�Y�����̉��H��S�����������A�\�A�����Y�Ƃ��Ĉ����p�����B�����Ƃ��ɁA�����ň��ʂ̌����͎Y�o������̂́A�����̐Ζ������L���p�V�e�B���ғ������邽�߂ɂ́A�����Y���������ł͕s�[���ł���A���܂�O���ƂȂ������V�A����̌����A�����������Ȃ��B�����āA���B�ɗאڂ���E�N���C�i�ƃx�����[�V�́A�Ζ����i�����B�s��ɔ̔������ŗL���Ȓn���I����������Ă���B
�@�������A�����ɂ́A�ߔN�̃E�N���C�i�ƃx�����[�V�̐Ζ������Ƃ̕��݂́A�D�ΏƂł���B�E�N���C�i�̐����������ނ̈�r��H��A����ł͂قډ�ŏ�Ԃɂ���̂ɑ��A�x�����[�V�ł͐Ζ������Ƃ��ő�̊�Y�Ƃɐ������A�A�o�̉҂����ɂȂ��Ă���B
�@�ȉ��A�{�e�ł́A�}�\�����p���A�E�N���C�i�ƃx�����[�V�̐Ζ������Ƃ��r�E���͂���B
�L�[�p�[�\���ɐu��
���V�A�Ζ������Ƃ̎�����ǂ����邩
�G�l���M�[�E���Z�������@������
A.�x���S���G�t
�@�{���ł́A���V�A�̃G�l���M�[�E���Z�������x���S���G�t�������̃C���^�r���[�����͂����܂��B�x���S���G�t�������́A30��O���Ƃ����Ⴓ�ł����A�O�E�̃G�l���M�[�헪�������Ζ����ォ��A���{�̃G�l���M�[�������Ɋւ��A���V�A�̃G�l���M�[����ɂ����č���̊����҂������Ƃ̈�l�ł��B����o�ώY�ƏȂ̎�����Ď��{���Ă��鎖�Ƃ̘g���ŁA�{�N2���P���`5���ɏ��߂ē��{��K��܂����B��������ѐV���ŃZ�~�i�[���J�Â��A���V�A�̐Ζ��K�X����̌���⒆�����I�W�]�ɂ��Ă����������܂����B�Z�~�i�[�̖͗l�ɂ��Ă͕ʓr�A���Љ��\��ł����A����͖K���ɐ旧���A���V�A�̐Ζ���������̌���ɂ��Ă��b���f���܂����B�����̒���≢�Ăɂ��o�ϐ��قƂ��������̉��A���̊�Y�Ƃ�1�ł���Ζ������Ƃ��ǂ̂悤�ȏɂ���̂��A���v�ǂ����\���������2015�N�̍ŐV�̃f�[�^�������ċ����[�����b�����Ă��������܂����B����ɁA����̓��{�̃r�W�l�X�`�����X�ɂ��Ă��A���ӌ������������܂����̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B�i���n���M�j
�~�j����|�[�g
�����X�������B�E�o�V�R���g�X�^�����a���ƐΖ�����
�@�Ζ����L�x�ȃ��V�A�ɂ͐Ζ��Y�Ƃ�����Ȓn�悪���������݂���B2011�N���烍�V�A�̐Ζ��Y�ƂɊւ��钲���Ɍg���A���n�����Ƃ��āA���X�N�������łȂ��A�Ζ�����ɋ����n���s�s���������K�₵�Ă����B���}���E�l�l�c�����Nj�i�T���n���h�s�j�A�^�^���X�^�����a���i�J�U���s�j�A�����X�������B�A�T�}���B�A�o�V�R���g�X�^�����a���i�E�t�@�s�j�Ƃ���������B���̂����A���}���E�l�l�c�ɂ��ẮA2012�N�T�����A�^�^���X�^���ɂ��Ă�2014�N�Q�����A�T�}���ɂ��Ă�2015�N�Q�����̌���ɂ��ꂼ��̖K��L�����M���Ă���̂ł���������Q�Ƃ������������B
�@����A��������K�₷��@��������X��������ŋߖK�₵���o�V�R���g�X�^���ɂ��Ă͂܂��\���ɏЉ�ł��Ă��Ȃ��B�����ŁA�{�e�ł͌��n�����œ��������܂��A�����X�������B�ƃo�V�R���g�X�^�����a���̊T���E�ߋ��ƐΖ������Ƃɂ�����B�i���n���M�j
�����ԎY�Ǝ��]
���V�A�E�E�N���C�i�ł̔r�K�X�K������
�@���V�A�ł�2016�N�������y���̊������������܂����B�K�\�����Ɋւ��Ă�2016�N�V���P�����狭�������\��ŁA����́A���V�A�����ł̓N���X�T�i���[���T�ɂقڑ����j�̌y���ƃK�\���������̔��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
�@����ƕ��������킹��悤�Ȍ`�ŏ�p�Ԃ̔r�K�X�K������������Ă���A2016�N�������烆�[���T�ɑΉ����Ă��Ȃ��A���ԁA���Y�Ԃ̐V�K�o�^���F�߂��Ȃ��Ȃ�܂����B����́A���V�A�̔r�K�X�K���������߂���Ƃ���ɑ����ʎs���̔����Ȃǂɂ��Ă��Љ�܂��B�܂��A�t�����ăE�N���C�i�̓����ɂ��G��܂��B�i�����j
�n��N���[�Y�A�b�v
�o�����X�̎�ꂽ�o�ύ\�������T���g�t�B
�@���V�A�ŐΖ����Y����ѐΖ������Ƃ��ł�����Ȓn��̂P�ł��鉈���H���K�A�M�Nj�͐Ζ��֘A�ȊO�̎Y�Ƃ�����ł���A�o�ϓI�ɍł����W�����n��ƌĂ�鏊�ȂɂȂ��Ă���B���̂��߁A�O����Ƃ̊S�������A�����̊O�����i�o���A���{����O�ł͂Ȃ��B���������w�i����A����ł��A������w���V�ANIS��������x�̓��W�Ƃ��ĉ����H���K�����グ�����т����B�����������ŁA�����H���K�n��S�̂Ɠ��A�M�Nj�Ɋ܂܂��ʂ̍\����̂ɒ��ڂ������A���ׂĂ�ԗ��ł��Ă����킯�ł͂Ȃ��B�����Ŗ{�e�ł͂���܂ŌʂɎ��グ���Ă��Ȃ������\����̂̂P�A�T���g�t�B�ɒ��ڂ���B�i���n���M�j
�����A�W�A���o�U�[��
�����A�W�A�E�R�[�J�T�X�̐Ζ���������
�@�{�e�ł́A�����A�W�A�E�R�[�J�T�X�̐Ζ���������ɂ��ďЉ��B���ɂ��̒n��ŐΖ����L�x�ȃJ�U�t�X�^���ƃA�[���o�C�W�����͍��ƌo�ς��Ζ����Y�E�A�o�ɑ傫���ˑ����Ă��邪�A�ߔN�͍����ł�荂���t�����l�����邱�Ƃ�ڎw���A�Ζ���������̋ߑ㉻�����̏d�v�ۑ��1�Ƃ��Ă���B���̂悤�ɐΖ���������ɊS�����߂�J�U�t�X�^���ƃA�[���o�C�W�����̓�����̌���Ɖۑ�ɒ��ڂ���B�i���n���M�j
���V�A��`�A���S���̖���
���V�ANIS�o�ό������@����
�V�����
�@�u�E���W�I�X�g�N�̋�`�A���S�������悢��J�Ƃ���B�E���W�I�X�g�N�E��`�Ԃ͍ŒZ42���Ō���A��`�ւ̃A�N�Z�X���傫�����P����v�B����ȋL�����������͍̂�����R�N���O�B�܂�������ȑ����P�ނ���Ƃ́B�A�G���G�N�X�v���X�Ђ�2015�N�Q�����A�E���W�I�X�g�N�ł̋�`�A���S���̉^�s����P�ނ����B�P�ތ�́A�n�����{���o��������c�S����Ђ��ׁX�Ɖ^�s����B�A�G���G�N�X�v���X�Ђ̓J�U���ƃ\�`�̋�`�A���S���̌o�c������P�ނ����B����J���̌��Ɖe�B���̎p�́A�V�����J�ʂɔ����ĕ��s�ݗ�����JR����藣����Ă��܂����{�Ƃǂ������Ă���B����͂܂����V�A�̒n���S���̌������o�c���Ԃ��f���o���B�����Ŗ{�e�ł́A�E���W�I�X�g�N�̋�`�A���S�����߂���o������ʂ��āA���V�A�̒n���S���̎��Ԃɂ��Ă܂Ƃ߂��B
�r�W�l�X�őO��
���Ȋw�@��̗A�o�Ń��V�A�̋���ƉȊw�ɍv��
�����f�Ճe�N�m���W�[��
������@��ӏ�F����
�@�����f�ՃO���[�v��1959�N���X�N���Ɏ��������J�݁B���N��57�N�ڂ��}���A�Y�Ƌ@�B�A�v�����g�A���Ȋw�@��̗A�o�A�����̗A���Ȃǃr�W�l�X��W�J����Ă��܂��B����́A�����f�Ճe�N�m���W�[�i���j�̐�ӎ�����ɂ��b�������������܂����B��ӎ������1986�N�Ƀ��X�N���ɒ��݂���č��N�ł��傤��30�N�ڂ��}�����܂��B���Ȋw�@��̗A�o�𒆐S�ɃC���^�r���[�����Ă��������܂����B�i�n粌����Y�j
�r�W�l�X�őO��
�t�����ł����P�[�u���E���C���n�[�l�X���Ƃ��g��
�t�W�N���@���X�N��������
���������@���J�B������
�@����A���Љ��t�W�N����1885�N�ɓd�����[�J�[�Ƃ��đn�Ƃ��A�ߔN�ł͓d���E�e��P�[�u���̑��A���ʐM���i�A�G���N�g���j�N�X�A�����ԓd���i�Ɏ��Ɨ̈���g�債�Ă��܂��B���V�A�ł����ِݗ����A���ʐM�Ǝ҂Ɍ��P�[�u����[�����Ă��鑼�A���{��Ƃ̑�������̑��ނ��̎����ɁA���V�A�Ń��C���n�[�l�X�H����I�[�v�����A����ɂ̓E�N���C�i�ɍH����J�݂��悤�Ƃ��Ă��܂��B����́A���������b����܂߂āA�t�W�N���̑��J�B�����X�N�����������ɂ��b�����f���܂����B�i�����F���j
�~�j�E���|�[�g
�}�����Œ��ڂ����C���N�[�c�N�Ζ����
�@���Ăɂ����o�ϐ��ًy�эŋ߂̋}���Ȗ����̉����Ƀ��V�A�̑����̐Ζ���Ƃ��Ώ��ɋꂵ��ł��钆�A����ł��C��f���đ��݊������߂Ă���Ɨ��n��ƂƂ��āA�C���N�[�c�N�Ζ���Ёi�ȉ��AINK�j����������B���{�ł͓Ɨ��s���@�l�Ζ��V�R�K�X�E�����z�������@�\�iJOGMEC�j��ɓ��������Ƌ����T�z���Ƃ��s���Ă��钆���Ζ���ƂƂ��Ēm���Ă���݂̂ł��邪�A���V�A�ł͍ŋ߁AINK�̋}�����U��ɒ��ڂ��W�܂��Ă���B�Ⴆ�Γ��Ђ́A2015�N�Ɍ����y�уK�X�R���f���Z�[�g�̔N�Ԑ��Y�ʂ�O�N���38������561.2�����ɂ܂ő��������Ă���A���̐��Y�ʂ�2008�N���_�̖�19�{�ɒB���Ă���B
�@�܂��ARBC����2011�`2014�N�܂ł̍����f�[�^���͂Ɋ�Â�2015�N11���Ɂu�}�������50�Ёv�����L���O�����\���Ă��邪�A�����ŕ��͑Ώۊ��Ԃɂ����锄�㍂�̕��ϐ���������44���ł��������Ɠ�����AINK��19�ʂɃ����N�C�������iRBC���͂��������������Ȃ��āAINK���u���������Ζ���Ƃɑ����Ȃ��ő�̐Ζ���Ɓv�ƕ]�����j�B���V�A�̐����҂���肪���ȈًƎ�ւ̎Q��Ȃǂɂ͂قƂ�NJS���������A�W�X�Ǝ��Ɗg��ɓw�߂Ă���_���o�ώ��ŕ]������Ă���B�ŋ߂ł́AINK�̑n�Ǝ҂ɂ��ē��Ў�������Љ�ł���j�R���C�E�u�C�m�t����Forbes���̕x�������L���O�ɓ��������Ƃ�����i���Y���z�͖�17���h���ƕ��Ă���j�A��v���ɃC���^�r���[�L�����Ƃ肠�����Ă���B�{�e�ł́AINK�̐ݗ��o�܂⎖�ƊT�v�ɂ��Đ���������ŁA���Ђ̌���ƓW�]�͂���B�i���J���Ɓj
�����������z
�g���X�g�C�ƃA�W�A�̎v�z�Ƃ����i�Q�j
�\����1�����O�K���f�B�[�ɑ������莆�\
�@1847�N��19�̐N�g���X�g�C�͕a�C�ŃJ�U���̕a�@�ɂ������A���ׂ̗̃x�b�h�Ɋ�ʂ��Ђǂ�������ꂽ���}���̑m���������B�g���X�g�C�͂��̑m�����珉�߂āu����R�v�̝|�̌[�����A�����S���U�̖z���̒���30�N�ԕۂ������邱�ƂɂȂ����̂ł���B���ꂩ��63�N���1910�N�ɁA�Ⴂ�C���h�l�K���f�B�[�͗ՏI�̃g���X�g�C�̎肩�炻�̐��Ȃ����������B����܂Ń��V�A�̘V���k�͂��̌����݂�����̈��Œg�߁A�݂�����̋ꂵ�݂ŗ{���A�����Ĉ�ĂĂ����̂ł������B�����ĎႢ�C���h�l�͂��̌��������ăC���h���Ƃ炷�x�i�����܂̉j�Ƃ����B���������̌��̔��˂͑S���E�̊e�n�y�̂ł���i���}���E���������u�g���X�g�C�̐��U�v���j�B�i��������j
INSIDE RUSSIA
���E���������̒��̃��V�A�s��
�@���̃R�[�i�[�Ƃ��Ă͎�ς��̘b��ł��邪�A����̓��V�A�̊����s��̊T�v�Ƌߋ��ɂ��ĉ�����Ă݂����B�������ŁA���E�I�Ȋ������L���钆�ŁA�ʂ����ă��V�A�̊����s��͌��݂ǂ��Ȃ��Ă���̂��낤���H�i�����ϑ�j
���V�A�ɓ����j��
�n�o���t�X�N�n���̋t�P
�@�V�^����Ȃǃv�[�`���������i�߂�V�����ɓ�����ŁA�n�o���t�X�N�n���̑��݊��������Ă���B�v�[�`�������̃E���W�I�X�g�N�d���̉e���ŁA�������N�͈�n���s�s�Ƃ��Ă��������Ă��Ȃ������B�Ƃ��낪�ŋ߂́A�v�[�`�������̋ɓ�����̖ڋʂ̂P�ł���V�^��������܂����p������A��Q�̓s�s�R���\�����X�N�i�A���[���̏W���Đ��ɒ������{�̂��n�t�������������ƃv���X�ʂ������A�Ăуn�o���t�X�N�ɒ��ڂ��W�܂��Ă���B�i�V�����j
���X�N���ւ�
�ƃ��ʏ���c���F�O�����̒��̍ő吨��
�@2015�N�����_�ŁA���V�A�ɂ�5,583�Ђ��̃h�C�c��Ƃ��o�^����Ă���A����̓��V�A�Ŋ�������O�����̒��ł���тʂ��đ����B�h�C�c�̃r�W�l�X�E�̓��V�A���d�v�Ȑ헪�I�s��Ƃ݂Ȃ��A�f�Ց���Ƃ������͓�����Ƒ����āA���X�ƌ��n���Y����i�߂Ă���B�h�C�c��Ƃ̒��ɂ́A�t�H���N�X���[�Q����V�[�����X�A�{�b�V���̂悤�ɁA���V�A�ɂ����ĕ����̐��Y���_���\���Ă���Ƃ�������Ȃ��Ȃ��B���V�A�ł�������������W�J����h�C�c��Ƃɑ��āA�l�X�ȃT�|�[�g���s���ƃ��ʏ���c���́A�݃��V�A�̊e�����H��̒��ł����݊��̂����ւ�傫���g�D�ł���B�����ł͓ƃ��ʏ���c���̊����ɂ��Ă��Љ�邱�Ƃɂ������B�i�����F���j
�Y�ƁE�Z�p�g�����h
���V�A�Ō����ł��Ȃ������ԕ��i�̕i��
�@���V�A�ɂ����鎩���Ԑ��Y�́A�̔��䐔�̑啝������ꋫ�Ɋׂ��Ă���B�����āA�̔��䐔�������łȂ��A���V�A�Ŏ����Ԃ̌��ޗ��E���i�����n���B�ł��Ȃ��Ƃ����g�`���I���h���A�X�ɋꋫ�ɒǂ������������Ă���悤���B���[�u�����ɂ��A�A�����i�̃��[�u�����ăR�X�g���啝�ɏ㏸���A���́g�`���I���h�͂����ł������オ���钆�A�R�X�g������������Ƃ����ݏo���Ă���B����ŁA���̖��́g�`���I���h�ł���̂ŁA�����̕��̓w�͂ɂ��ꕔ�ł͉��P���i��ł����B���̌��ʁA���n���B�ł���i�ڂƌ��n���B�ł��Ȃ��i�ڂ����݂��邱�ƂɂȂ�A����Łg���n���B�͉\�h�Ƃ��������o�āA����Łg���n���B�͍���h�Ƃ�����������A��肪�����ɂ����Ȃ��Ă���Ǝv���B�����ԕ��i�͑��푽�l�Ȃ��̂�����A�i�ڂɂ���ď���̐������قȂ�B�i�ڂ���肵�Ȃ���A�Ȃ����n���B���ł��Ȃ��̂����킩��Ȃ����A����ł��Ȃ��B���������A�{���Ɍ��n���B���ł��Ă��Ȃ��̂�����킩��Ȃ��B���̏�ł��A�Q���_����i�ڂ̏ڍׂ܂Ŗ��炩�ɂ��Ă������Ƃ͂ł��Ȃ����A�������ɂ������邪�A����܂œ��Ă������A�ǂ̂悤�ȕ��i�����B�ł��A�ǂ̂悤�ȕ��i�����B�ł��Ȃ����̑�G�c�ȕ����𖾂炩�ɂ������Ǝv���B�i�n粌����Y�j
�E�N���C�i�������_
2015�N�̃E�N���C�i�V�R�K�X����̎���
�@����́A�}�\����g���A2015�N�̃E�N���C�i�̓V�R�K�X�ɂ�����铝�v�������Љ��B�V�R�K�X�̐��Y�A�A���A����A�g�����W�b�g�A���̏����Ă������Ƃɂ���B�i�����ϑ�j
�f�W�^��IT���{
���V�A�̃R���s���[�^�Q�[���s��
�@���X�N���ɏZ��ł���ƁA�o�X��n���S�̎ԓ��A��s�A�a�@���̌����X�y�[�X�ɂ����āA��p�v���C���[��X�}�[�g�t�H�����̃f�o�C�X���g���ĉ��y�⓮�����������l�A�d�q���Ђ�ǂ�ł���l�����������邱�Ƃ������A���V�A�l�̃f�W�^�����C�t����������ɂ��Ă����悤�Ȉ�ۂ��鍡�����̍��B����́A�ɂ�������Ζ����A�v���̃v���C�ɋ��݂��A�����ŋ߂̃Q�[������ɂ͑S�����Ă����Ă��Ȃ��M�҂��A���V�A�̃R���s���[�^�Q�[���s��ɂ��ĊT�v���܂Ƃ߂Ă݂��B�i��n�k�O�j
���W�X�e�B�N�X�E�i�r
�`�p�E�S���������2015
�@2015�N�̃��V�A�o�ς͐[���Ȍo�ς̎��������炩�ɂȂ��Ă��܂����A��������ɖڂ�������ƌi�C�����ɂ�����ɂ��Z�W�����邱�Ƃ�������܂��B���J���ꂽ2015�N�̑���l����S�̓I�X����ǂ݉����܂��B�i�ҋv�q�j
�R�������ܘb
���V�A�E�T�b�J�[�N���u�̃p�[�g�i�[�ƃX�|���T�[
�@�]���A���n��Ƃ����V�A�E�T�b�J�[�E�Ƌ��Ƃ��邱�Ƃ́A���܂�Ȃ������悤�Ɏv���B�������A2015�N�ɂ͕����̓��n��Ƃ����V�A�̗L���ǂ���̃T�b�J�[�N���u�ƃp�[�g�i�[�_������ԂƂ����A�������Ȃ��������������B�����o�ϊW�ɒ���[�h���Y�����ŁA���邢�b��ƌ����悤�B�����ō���̖{�R�[�i�[�ł́A2015�N�ɐ����������n��Ƃƃ��V�A�E�T�b�J�[�N���u�̒�g�W���A�܂Ƃ߂Ă������Ƃɂ���B
�@�܂��A���݂̂Ƃ�����n��Ƃƃ��V�A�E�T�b�J�[�N���u�̃R���{�́u�p�[�g�i�[�v�Ƃ����i�K�ł��邪�A���コ��ɓ��ݍ���Łu�X�|���T�[�v�̖������ďo���Ƃ��A������������o�Ă��邩������Ȃ��B�����ŁA�����_�łǂ�Ȋ�Ƃ����V�A�E�v���~�A���[�O�e�N���u�̃[�l�����X�|���T�[�i���̕t�����C���X�|���T�[�j�ɂȂ��Ă��邩���A���킹�ă`�F�b�N���Ă݂邱�Ƃɂ���B�i�����ϑ�j
�V�l�}����ב��I�I
���z�I�q���C���̑n����
�w�M���̑��xVS�w���̔ߌ��x
�@ �v���A���V�A���w��V�A�i�\�A�j�f��̃q���C�������́A���ꂼ��̐��i��^���A�������≿�l�ςɈႢ��������A��������A������u�i���̏����v�͂��܂��u�^���̏����v�Ƃ��āA���鎞�͒j���ɃC���X�s���[�V�����∤�̊�т�^���A�܂����鎞�͒j����j�łɒǂ����ނƂ����A���ɖ��͓I�ȏ�������ł��B�����̃��V�A�̌|�p��i���A�������������̖��͂Ɣ������A�������邢�͖�����`�����߂ɕ������Ă���ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��ł��傤�B��N�̂��̗��i�R�����j�ɂ����ẮA���V�A�̓y��ɂ̓t�F�~�j�Y���̎v�z���炿�ɂ����A�ނ���A�ِ��ɂƂ��Ă˂ɖ��͓I�ł���悤�ɐU�镑���A���������ɂ��鏗���������Ƃ�����|�̂��Ƃ������܂������A�����ɁA�j������������̂��Ƃ����߁A���z�����A�����Ƃ��Čh�ӂ��X�����A�t�F�~�j�Y�����Z�����Ȃ����������߂Ȃ̂��A19���I����Љ��`�̎�����o�Ă��Ȃ��A�����č����Ɏ���܂łȂɂ��������̂悤�Ȃ��̂Ƃ��āA���葱����悤�Ɏv���܂��B���̂��т́A�u���ەw�l�f�[�v�Ɉ��݁A�������j�����琒�߂��郍�V�A�̗��z�I�������ɂ��āA�c���Q�[�l�t����̉f��w�M���̑��x�i1969�j�ƃ`�F�[�z�t����́w���̔ߌ��x�i1978�j�ɓo�ꂷ��q���C�������ɂ��čl���Ă݂����̂ł��B�i������o���j
�L�҂́u��ʑI���v
�_�̃��J�T�M�ނ�F覐Δ�������R�N
�@���V�A�E�E�����n���̕S���s�s�`�F�����r���X�N�̏���覐��������A�r��Ȕ�Q�������炵�Ă���A���̂Q��15���łR�N�ɂȂ�B���̓��A����覐�ǂ������Č���ɋ}�s���A���s�̐���70�L���̃`�F�o���N���ɗ������ǂ蒅�����B�g���b�N���n��镪�����Ζʂ̕X����������a�W���[�g���قǂ̌����A���̒܍��������B�������E�ɂۂ���ƌ��ꂽ�ΐ��́A�����̋���z�����悤�ȔZ���B覐��d��ɂ��āA�_�l�����̌��Ń��J�T�M�ނ�ɋ�����p����z�����B�i���F�G���j









