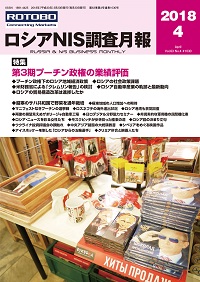 |
|
���V�ANIS��������2018�N�S�������W����R���v�[�`�� |
|
���W����R���v�[�`�������̋Ɛѕ]�� |
|
�������|�[�g |
�v�[�`���������̃��V�A�n��o�ϐ��� �\�k�Ɉ�̎����\�ȊJ���\ |
�������|�[�g |
���V�A�̎Љ��ۑ� �\�v�[�`��������R���̎�g�ƌ���\ |
�������|�[�g |
�č����Ȃɂ��u�N���������v�̌��� |
�������|�[�g |
���V�A�����ԎY�Ƃ̋O�ՂƍŐV���� �\�v�[�`��������R���̑����\ |
�������|�[�g |
���V�A�̖f�Ս\�����v�͐i�������� |
�r�W�l�X�őO�� |
�����̃T�n���a���Ŗ��ʔN�͔| |
���V�A�ɓ����j�� |
�ɓ��n��̐l�������ւ̊��� |
INSIDE RUSSIA |
�}�j�t�F�X�g�Ȃ��v�[�`���̑I���� |
�G�l���M�[�Y�Ƃ̘b�� |
���X�l�t�`�̊C�O�i�o�� |
���W�X�e�B�N�X�E�i�r |
���V�A�`�p���i�C�� |
�����ԎY�Ǝ��] |
�Č��̓W�]�����ʃU�|���[�W�������ԍH�� |
�f�W�^��IT���{ |
�����f�W�^�����싦�̓Z�~�i�[ |
�Y�ƁE�Z�p�g�����h |
���I�ȌR�p�@�̖��ԋ@���� �\�����������@�͗��q�@�ɂȂ�Ȃ��\ |
���V�A���f�B�A�ŐV���� |
���V�A�E�j���[�X���ʂ鏗������ |
���V�A�Ɠ��{�E �o��̕��i |
���X�N�r�b�`������������ɓ��̓� |
���݈��̃��V�A�� |
���V�A��̌��܂蕶�� |
�E�N���C�i�������_ |
�E�N���C�i�����]�c��̊�G�� |
�����A�W�A���o�U�[�� |
�����A�W�A�����̑哝�̋��� |
�V�l�}����ב��I�I |
�V�x���A���߂���f���i |
�X�������ܘb |
�A�C�X�z�b�P�[�𐧂����u���V�A����̌ܗ֑I��v |
�ƊE�g�s�b�N�X |
2018�N�Q���̓��� |
�ʊ֓��v |
2018�N�P���̗A�o���ʊ֎��� |
�L�҂́u��ʑI���v |
�N���~�A�����Ɖf��l���� |
�������|�[�g
�v�[�`���������̃��V�A�n��o�ϐ���
���V�A�Ȋw�A�J�f�~�[���Ǘ������Z���^�[�@��C������
O.�N�Y�l�c�H���@
�@�����̏��O���Ɠ��l�A���V�A�̒����ƒn���̌o�ϊW�͈ȉ��̂Q�̑傫�ȗv�f���琬��B�@�قȂ郌�x���̌��͋@�ւ̊Ԃł̗\�Z�����̔z����ۏႵ�A�n��̗\�Z�m�ۂ̋ύt����ڎw���g�g�݂Ƃ��Ă̗\�Z�ԊW�B�A�n��̎Љ�o�ϔ��W���x���ɂ�����i�����ɘa���A���������n��̌o�ϐ����̏����𐮂��邱�Ƃ�ړI�Ƃ���n�搭��B
�@�\�Z�ԊW�ƒn�搭��́A�����I�Ɂu�������Ă���v���A����͒n�搭��̃c�[���̒��ɒ����E�n���Ԃ̍����ړ]�i�A�M�\�Z����n���n�������\�Z�ւ̍����ړ]�j�����邩�炾�B�������A�S�̓I�Ɍ����ꍇ�A�����ƒn���̌o�ϊW�͂����܂œƗ��������傾�Ƃ�����B�\�Z�ԊW�Ɋւ��ẮA���E�e���Ɠ��l�ɁA���V�A�ł������Ȃ��S�����Ă���A�n�搭��ɂ��ẮA�o�ϔ��W�Ȃ��S�����Ă���B
�@��R���v�[�`���������n�܂�O�̎��_�Ń��V�A�ɂ́A���ł�2000�N�㔼�Ɍ`�����ꂽ�\�Z�ԊW�V�X�e�������݂����B2012�N�ȍ~�ɂ��̃V�X�e���Ɉ��̕ύX�������炳�ꂽ���i��q�j�A�\�Z�ԊW���\�z�����ł̑S�ʓI�Ȍ�����A�v���[�`���@�͂���܂łƂ���ł������B
�@�����A�n�搭��Ɋւ��Ă͑S���قȂ�������Ă����B��R���v�[�`���������n�܂������_�ł͂��̌`���v���Z�X���܂��������Ă��Ȃ��̂͒N�̖ڂɂ����炩���������A���̈���ŁA���̍����łɔ��{�I�ȕω��������Ă����̂������ł���B���Ƃ��A�n�搭��̐V�����@��Ղ̐�����Ƃ��J�n����A�g�D�I�Ȋ�Ձi�n��̎Љ�o�ϔ��W�ɐӔC�����A�M�@�փV�X�e���j�ɂ��ω��������Ă����B����ɂ́A�n�搭��̐V�����g�D��c�[�����o�ꂵ�A�ߋ��ɓ������ꂽ�n��̎Љ�o�ϔ��W�ɑ���A�M���{�̎x�����J�j�Y���ɏC����������ꂽ�B�ȉ��ŁA�������ׂĂ̖��ƘA�M���{�̒n�搭��̐��ʂ�������A�ɓ��̖��ɂ��œ_�����Ă邱�Ƃɂ���B
�������|�[�g
���V�A�̎Љ��ۑ�
�\�v�[�`��������R���̎�g�ƌ���\
�ꋴ��w�o�ό������@����
�_�a�L
�@2012�N�Ɏn�܂�����R���v�[�`��������2018�N�T���ɂ��̔C�����I����B2012�N�̑哝�̏A�C��A�v�[�`�����͂��̔C�����̖ڕW��D�悷�ׂ�����Ɋւ��哝�̗߂��A�A�C���X��p�����ɔ��z�����B�{�e�͂Ƃ�킯���̎Љ��Ɋւ��ۑ�ɂ��āA������ēx�m�F����ƂƂ��ɁA����ɉ����`�ŋ�̓I�ɂǂ̂悤�Ȑ��������ꂽ�̂��A�����ĉʂ����Ă��̂U�N�Ԃł����ڕW�͒B�����ꂽ�̂��ۂ��A�����Ă������Ƃ��|�Ƃ�����̂ł���B
�@2012�N�T���V���ɂ�����哝�̏A�C�Ɠ����ɔ��z���ꂽ�哝�̗߂̂����A���ł��s�������ɒ�����������̂Ƃ��ẮA�u���ƎЉ������̂��߂̑[�u�ɂ��āv�A�u�l��������������邽�߂̑[�u�ɂ��āv�A�u�s���Ɏ荠�ʼn��K�ȏZ�����Z��E���c�T�[�r�X�̎������コ���邽�߂̑[�u�ɂ��āv�A�u�ی�����ɂ����鍑�Ɛ���̉��P�ɂ��āv�̂S�������邱�Ƃ��ł���B��A�̑哝�̗߂ɂ����Ėڂ��䂭�̂́A���m�Ȑ��l�ڕW���グ���Ă��邱�Ƃł���B�Љ�w�W�ɂ��Ă����܂Ŗ��m�Ȏw�W���������Ƃ��ʂ����đÓ��ł���̂��ۂ��A���̔��f�͍���ł��邪�A�v����Ԗ�����ɂ����鎑���z��������ژ_��ł����Ƃ���Ȃ�i���������Ȃ��Ɨ\�������w�W�������A���̂̂����̗̈�ւ̏d�_������e�ՂȂ��̂Ƃ��邱�Ƃ�ژ_��ł����̂ł���j�A�헪�I�ȑÓ��������邩������Ȃ��B�������\�Ȃ��̂ƌ��Ȃ��Đݒ肵�Ă����Ƃ���A����͂��Ȃ芊�m�Ȋς�^����ꍇ�����蓾��B�����̌��������A�܂��M�҂̐��̈�̌�������邽�߁A�����ł͏�q�̂S�̑哝�̗߂ɓI���i���Č������s���B
�������|�[�g
�č����Ȃɂ��u�N���������v�̌���
���m��w�@�l���w��
�����r�F
�@��R���v�[�`���������ŁA�}�炸���d�v���ƂȂ����̂��A���Ă̑��V�A���ق������B
�@�č����Ȃ�2018�N�P��29���[��A������u�N���������v�����\�����B����́A2017�N�W���Q���Ƀh�i���h�E�g�����v�đ哝�̂����������u���ق�ʂ����č��̓G���i�C�����A���V�A�A�M�A�k���N�j�ւ̑R�@�v�̃Z�N�V����241�̋K��Ɋ�Â��č쐬���ꂽ���̂ł���B�@���s��A180���ȓ��ɍ��������͍��Ə���ƍ��������Ƃ̋��c�̂��Ƃɋc��ψ���ɑ��āA���V�A�����ɋ߂��Ɩڂ����O�𐭍�ɂ�����鐭�{������I���K���q�i�V�������j�̃��X�g���o���邱�ƂɂȂ��Ă����B�����A�v�[�`���ɋ߂��ƕč����{�����f���Ă���A���ّΏۂƂȂ肤��l�����������ƂŁA�r�W�l�X��̒��ӊ��N�ɂȂ���˂炢������B
�@�{�e�ł́A�����ɂ��郊�X�g�Ɏ��ڂ��ꂽ�S����\�P�ƕ\�Q�ɕ����ďЉ�Ă���B�\�P�ɂ́u�����I�w���ҁv�Ƃ��āA�哝�̕{�A���t�A���̑��ɕ����č��v114�l��������Ă���B�\�Q�ł�96�l�̃I���K���q������o���Ă���B���v��210�l�ŁA�I�o�}�������ł��łɐ��ّΏۂ�����22�l���܂܂��B�����ł́A�\�P�ƕ\�Q�ɕ����Ă��̓��e���Љ�Ȃ���A���_���w�E���Ă݂����B
�������|�[�g
���V�A�����ԎY�Ƃ̋O�ՂƍŐV����
�\�v�[�`��������R���̑����\
���V�ANIS�o�ό������@����������
�����
�@�}���ȐΖ��̑��Y�ƍ������������Ɏx����ꃍ�V�A�̐V�Ԕ̔��䐔�́A2000�N�㔼���납��E���オ��̋Ȑ���`���n��2012�N�ɂ�294����iLCV���܂ސ����j�Ƃ����ߋ��ō��̐����ɒB�������A2013�N����͈�]���ĉ��~�������ǂ�悤�ɂȂ����B���V�A���{���l�X�Ȕ̔����i�����ł��o�����ɂ�������炸�A�s�U�̓x�����͔N�X�[���ƂȂ�A2016�N�̔̔��䐔��2012�N�̔����ȉ��̖�143����ɂƂǂ܂����B�������A2017�N�ɓ��茎�Ԕ̔��䐔���O�N�����̐���������P�[�X���ڗ����n�߁A�ʔN�̐����͑O�N��11.9�����̖�160����ɒB�����B�̔��̊ϓ_���猩��A2012�`2017�N�̓��V�A�s��̉h�͐������Ïk���ꂽ���Ԃ������Ƃ����悤�B���Y�̊ϓ_���猩���2012�`2017�N�́A2005�N�ɓ������ꂽ�H�ƃA�Z���u���[�u�̐��ʂ������I�ɂł͂��ꌰ�݉��������Ԃł������Ƃ�����B�H�ƃA�Z���u���[�u�̎�ړI�̂ЂƂ͊O���n�����ԃ��[�J�[�̍H������V�A�ɗU�v���邱�Ƃł��������A���̓_�ɂ��Ă͌����Ȑ��ʂ������Ă���A2005�N�ȍ~�A���V�A�̏�p�Ԑ��Y�䐔�ɐ�߂�O���u�����h�Ԃ̐��͋}�����A2010�N�ɂ͎j�㏉�߂ď����Y�u�����h�Ԃ̐��Y�䐔����ł͂��邪�������B���̌�A�i�C�����ɔ��������Y�䐔�͖��N�ω����Ă��邪�O���u�����h�Ԃ̃V�F�A�͈�т��đ������Ă���A2017�N���_�ł̓��V�A�Ő��Y������p�Ԃ̖�S���̂R���O���u�����h�ԂƂȂ��Ă����B
�@�{�e�ł́A���{���ł��o���������ԎY�ƐU�����V�A�̏�p�Ԏs��̓����ɒ��ڂ��Ȃ���A�v�[�`����R���������̃��V�A�̎����ԎY�Ƃ���ڂ���B
�������|�[�g
���V�A�̖f�Ս\�����v�͐i��������
���V�ANIS�o�ό������@������
�����ϑ�
�@�v�[�`�������́A���V�A�̌���̖f�Ս\�������P��v������̂ł���Ƃ̖��ӎ���L���Ă���A��R��������ʂ��Ă��̉ۑ�Ɏ��g��ł����B��̓I�ɂ́A���[���V�A�������e�R��CIS����f�Ղ̊g���}�邱�ƁA���B�ɕΏd�����f�Ւn��\�������A�W�A�E�����m�s��ɃV�t�g���邱�ƁA��A�̕���E�i�ڂŗA���Ɉˑ����Ă����Ŕj���A����ւ𐄐i���邱�ƁA���E��G�l���M�[���i�̗A�o�A�Ƃ�킯�@�B���i�̗A�o���g�傷�邱�ƁA�Ƃ������ۑ�ł���B�{�e�ł͂����̉ۑ���u�f�Ս\�����v�v�Ƒ��̂�����ŁA�}�\�𑽗p���A��R���v�[�`�����������̕���Ōf���Ă����ڕW���ǂ����������̂��������A���̌㐭�ǂ̂悤�ɕϑJ���Ă��������A�����Ď��ۂ̐��ʂ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂����������A�T�ς���B���|�[�g�̐��i��A�M�҂̊������|�[�g�Ɠ��e�I�ɏd������Ƃ�������Ȃ��Ȃ����A���e�͊肢�����B
�r�W�l�X�őO��
�����̃T�n���a���Ŗ��ʔN�͔|
���z�b�R�E�@��\�������
�{�{�x�N����
�@���V�A�ɓ��E�T�n���a���̃��N�[�c�N�s�ŁA�������͂ɂ���̉����͔|�v���W�F�N�g�������n�߂Ă�����������Q�N�ɂȂ�܂��B���{���Ŗk�C�����������ƃ^�b�O��g�݁A�_�Ɛ��Y�̋Z�p�T�|�[�g�����ɒS���̂����z�b�R�E�i�D�y�s�j�ł��B�^�~�Ƀ}�C�i�X60�x�ɉ�����Ɋ��̒n�ŒʔN�̃g�}�g�͔|�ɐ������A�ډ��A�{�݂̊g��H���Ɍ�����������Ƃ�i�߂Ă��܂��B�{�{�x�N�В��Ƀ��V�A�i�o�̌o�܂�l�������f���܂��B�i�g���T�i�j
���V�A�ɓ����j��
�ɓ��n��̐l�������ւ̊���
�@���V�A�ɓ��̐l�������ɁA�悤�₭���~�߂�������Ƃ���܂ł����B���V�A�̐l����2009�N�Ɉꑫ���������ɓ]���Ă������A�ɓ��n�悾���͌����������Ă����B���V�A�A�M���v�ǂ����\�����Ƃ���ɂ��ƁA2018�N�����݁A���V�A�ɓ��̐l����616��2, 427�l�i���v�l�j�ƁA�����͑����Ă�����̂́A���̐����͎�܂�A�������͑O�N�Ɣ�ׂĖ�Q���l�A���ɂ���0.3���̒ቺ�ɂƂǂ܂����B�ߔN�A�l�������ɂ悤�₭���~�߂�������̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂���������悤�Ȗ��邢�����������n�߂Ă���B �i�V�����j
INSIDE RUSSIA
�}�j�t�F�X�g�Ȃ��v�[�`���̑I����
�@�l�I�ɁA�P���A�Q���ƃ��V�A�ɏo������@�����A��A�̒n���s�s��K�₵���B�哝�̑I����̂��Ȃ��ł���ɂ�������炸�A���V�A�؍ݒ��A���̕��͋C���قƂ�NJ����Ȃ������B�đ哝�̑I�̂悤�Ɍ��ғ��m�̓��_��Ƃ��������ꂪ����킯�ł͂Ȃ��i����ɂ͂��邪�A�{���v�[�`���͎Q�������A�A����₽���ɂ��TV�^�b�N���I�Ȃ��̂ɂ����Ȃ��j�A���{�̑��I���̂悤�ɊX���������I���J�[�����҂̃|�X�^�[������킯�ł��Ȃ��A�Ƃɂ����I���炵���C�x���g��A�C�e�����R�����̂ł���B
�@����̑I����ł́A�v�[�`���w�c�̓}�j�t�F�X�g�I�Ȃ��̂������\�����Ȃ��܂܁A�����̐R���������ƂƂȂ����B���̌��ʁA�R���P���Ƀv�[�`���哝�̂��s�����N�������������A�����I�ȑI���j�̂̂悤�ȈӖ�������тт邱�ƂɂȂ����B�i�����ϑ�j
�G�l���M�[�Y�Ƃ̘b��
���X�l�t�`�̊C�O�i�o��
�@���V�A���c��Ɓu���X�l�t�`�v�͈ȑO����x�l�Y�G�����͂��߂Ƃ��鏔�O���̃v���W�F�N�g�ɐϋɓI�Ɏ��g��ł��܂������A�ŋ߂ɂȂ�A���Ђ̊C�O�i�o�̈ӗ~�͂���ɍ��܂��Ă��܂��B2016�N�ɂ̓o�V�l�t�`�̔����ɔ����A�C���N�ƃ~�����}�[�̃v���W�F�N�g�Ɋ֗^���邱�ƂɂȂ�܂����B����ɁA2017�N�ɂ̓G�W�v�g�̑嗤�I�̑�K�̓K�X�z���̌��v��30���h����Ŕ����������A�C���h�̐������uEssar Oil�v�̊����̖�49����40���h����Ŕ������Ă��܂��B���̑��A2017�N�Q���ɂ̓N���h�������{�Ƃ̊ԂŁA�Ζ��̍w���_���������O���Ƃ���13���h�����x�������Ƃ����Ă��܂��B���X�l�t�`�̊O���ł̃v���W�F�N�g�̒��ɂ́A�N���h�������{�Ƃ̌_��̂悤�Ƀ��X�N�̍������̂����Ȃ�����܂��A����͂��̓_�ɗ��ӂ��Ȃ���A���X�l�t�`�̊O���ł̃v���W�F�N�g�ւ̎��g�݂��݂Ă��������Ǝv���܂��B�i�����j
���W�X�e�B�N�X�E�i�r
���V�A�`�p���i�C��
�@�}�N���o�ώw�W�̉𗠕t����悤�ɁA2017�N�̃��V�A�`�p�̎戵�ʂ��͋��������O����`���n�߂܂����B�ŐV�̃��V�A�`�p���v�Ɋ�Â��戵���т͂��܂��B�i�ҋv�q�j
�����ԎY�Ǝ��]
�Č��̓W�]�����ʃU�|���[�W�������ԍH��
�@�U�|���[�W�������ԍH��iZAZ�j�́A�鐭���V�A����ɑk��`�����ւ�A�E�N���C�i���\�����p�ԃ��[�J�[�ł��B�������A�ߔN�͋Ɛт̒���������A�Č��̓W�]���`���Ȃ��ł��܂��B�i�����ϑ�j
�f�W�^��IT���{
�����f�W�^�����싦�̓Z�~�i�[
�@2��12���`20���ɂ����āA���{�̃X�^�[�g�A�b�v�W�҂����V�A��K��A���X�N���A�J�U���A�T���N�g�y�e���u���O�ŃZ�~�i�[���J�Â����B�M�҂̓��V�ANIS�f�Չ�̈˗����A�r�W�l�X�R���T���^���g�Ƃ��āA���C�x���g�̊�旧�Ă�����{���E���V�A���Q���҂̏W�q�A����̃R�[�f�B�l�[�g�APR�헪�Ɏ���܂ŁA���ׂẴv���Z�X�Ɋւ�点�Ē������B���̏����č���̃C�x���g�̕��������Ǝv���B�i�q�슰�j
�Y�ƁE�Z�p�g�����h
���I�ȌR�p�@�̖��ԋ@����
�\�����������@�͗��q�@�ɂȂ�Ȃ��\
�@2018�N1��25���A�\�A���J��������������^�����@Tu-160�̉����ł��v�[�`���哝�̂ɔ�I���ꂽ�B���炭�͌��s�@�̉����ʼn����ł����邪�A�����I�ɂ�Tu-160�̐������ĊJ����Ƃ̂��Ƃ��B���̐Ȃ̈��A�ŁA���q�@�ɉ������Ă݂Ă͂ǂ����Ƃ����A�C�f�A�������ꂽ���Ƃ����ꂽ�BTu-160�͌����_�Ŕ�s���鐢�E�ő�̒������@�ŁA�č��̃J�E���^�[�p�[�g�ƂȂ�B-1�����@���@�̋K�͂ł��ō����x�ł����킷��B�܂��ɁA���V�A�̍��x�ȍq��Z�p�������@�̂ł���B�q��@�̋K�͂̎w�W�Ƃ��ėp������ő嗣���d�ʂ�Tu-160�ł�275���ł���A�A�G���t���[�g������-���X�N�����ɏA�q�����A250���ȏ�̏�q���悹�邱�Ƃ��ł���G�A�o�XA330��230�����A�ꌩ����ƁA�\���ɉ\��������悤�Ɍ�����B����͂��̋Z�p�I�������ɂ��Č�������B�i�n粌����Y�j
���V�A���f�B�A�ŐV����
���V�A�E�j���[�X���ʂ鏗������
�@�ŋ߁A���V�A�̃j���[�X�ɂ悭�o�Ă���A3�l�̏����ɂ��Ă��Љ�܂��B�l�ƂȂ��m��ƁA�j���[�X��ǂނ̂������y�����Ȃ邩���H�i���R�������j
���V�A�Ɠ��{�E�o��̕��i
���X�N�r�b�`������������ɓ��̓�
�@�ɓ��Ƃ����͎̂����܂߂ă��V�A�l�ɂƂ��Ă��{���ɋɒ[�ɉ����A�s���@����Ȃ��i���邢�́A�Ȃ��j�n��ł����āA�悭�m���Ă��Ȃ����V�A�̑傫�Ȉꕔ���B���͂����Ɠ��{�ɊW����d�������Ă���̂ŁA���{�ɋ߂��ɓ��ɂ�����I�ɒʂ��Ă���̂����A�Ⴆ�A���̉Ƒ�3�l�A���e��e�ʁA��ЈȊO�̑����̗F�����̒��ł́A��x�ł��ɓ��ɍs�������Ƃ�����l�͈�l�����Ȃ��B�iD.���H�����c�H�t�j
���݈��̃��V�A��
���V�A��̌��܂蕶��
�@���V�A��ł��A��������ꂽ��A�����Ԃ��Ƃ����̂�����A��������Ȃ��Ǝ���ɂȂ邱�Ƃ�����̂Œ��ӂ��K�v���B���Ƃ��A���V�A���T�E�i����オ���Ă����l�� �R �|�v�s�{�y�} ���p�����}!�i�������ł����ˁj�Ɛ��������A����������ꂽ���̈́R���p���y�q���i���肪�Ƃ��j�Ɠ�����B�܂��H���O�E���� �P���y�����~���s�� �p�����u���y���p! �i�����オ�� = bon appetit�j�ƌ���ꂽ��A�K���R���p���y�q���ŕԂ��B���̂悤�Ȃ���u�����̎�E���Ɓv�Ƃł������\���͂܂��܂�����B�i�V�䎠�j
�E�N���C�i�������_
�E�N���C�i�����]�c��̊�G��
�@�E�N���C�i�̃|���V�F���R�哝�̂�2017�N10��10���A�u���Ɠ����]�c��v�̃����o�[���߂��哝�̗߂ɏ��������B���Ɠ����]�c��Ƃ����̂́A�����U�v�Ɋւ��鎐��@�ւł���A�E�N���C�i�̐��������ɉ����āA�O�����{�̑�\�҂�����A�˂Ă���B��������āA�M�҂͊�@�����o�����B���Ă͂������A������؍��̑�\������A�˂Ă���̂ɁA���{������،�������Ȃ���������ł���B�i�����ϑ�j
�����A�W�A���o�U�[��
�����A�W�A�����̑哝�̋���
�@2017�N�R���P���A�哝�̑I���T�������V�A�Ńv�[�`���哝�̂��N�������������s�����B�N�Ɉ�x�̑哝�̂̎{�����j�����Ƃ������ƂŖ��N�S���W�߂Ă��邪�A����͑哝�̑I���̒��O�Ƃ������Ƃŗ�N�ȏ�ɒ��ڂ��W�܂����B���̂悤�ȑ哝�̂ɂ��N�����������Ƃ����̂͒����A�W�A�ł��s���Ă���B���V�A�قNJS���������邱�Ƃ͂Ȃ����A���V�A�ȏ�ɑ哝�̂������ɑ傫�ȉe����^���鍑������A���������͒P�Ȃ鉉���ɗ��܂炸�A�d�v�Ȑ�����Ӗ����邱�Ƃ�����B�����Ŗ{�e�ł́A���߂ɍs��ꂽ�����A�W�A�e���̑哝�̋�������e���̐���̕������ɂ��ďЉ�Ă݂����Ǝv���B �i���n���M�j
�V�l�}����ב��I�I
�V�x���A���߂���f���i
�w�V�x��������xVS�w�V�x���A�[�_�x
�@������V�x���A�i�ɓ����V�A�������j�����V�A���x�z���ɂ������̂�16���I�A���̃C�F���}�[�N�ɂ��V�r���E�n�����U���ɒ[����Ƃ���܂��B�������V�x���A�̎�s�Ƃ�����m���H�V�r���X�N���s�s���`�����Ă������̂�19���I���ł��̂ŁA���̊J��̌o�܂���j�������ɐ���Ȃ��̂ł��������z���ɓ����܂���B��Z�����ւ̗}����V�A������ɑ���ᔻ�����@���ꂽ�킯�ł͂Ȃ��ł��傤���A�������A�s���Ȏ��R���Ƃ̓��������̊�Ղɂ������ł��傤�B���̏��Ƃ��ăV�x���A�̎��R����炸�ɂ͐��������Ȃ����w��i��f��͐������n���Ă��܂����B���̂��т́A�^�C�g���ɂ��V�x���A�̒n���f�����Q�̉f���i������ׂĂ݂����̂ł��B�i������o���j
�X�������ܘb
�A�C�X�z�b�P�[�𐧂����u���V�A����̌ܗ֑I��v
�@�u�R�������ܘb�v�̃R�[�i�[�͎��X�A�u�X�������ܘb�v�ɉ�����B2017�N�Q�����ɑ����āA����̓A�C�X�z�b�P�[�̘b������͂��������B�����܂ł��Ȃ��A�����~�G�ܗւ̒j�q�A�C�X�z�b�P�[�Ń��V�A�E�`�[�����D����������ł���B�i�����ϑ�j
�L�҂́u��ʑI���v
�N���~�A�����Ɖf��l����
�@�u�����͋���Ȃ��B����20�N���|���͂Ȃ��B���ʼn��ꂽ�����Ȓj���x�z���鎞��͂����Ƒ����I���ƁA���͒m���Ă��邩��v�B2015�N�S���W���A���X�N���̒n��ٔ����B�N���~�A�����ł̃e���v��̍߂Ń��V�A���ǂɋN�i���ꂽ�E�N���C�i�̉f��ēI���N�E�Z���c�H�t�͋���A���������������B�i���F�G���j









