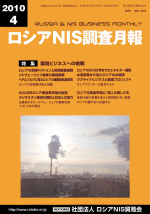|
|
ロシアNIS調査月報2010年4月号特集◆環境ビジネスへの挑戦 |
|
3月20日発行 |
特集◆環境ビジネスへの挑戦 |
|
調査レポート |
ロシアの気候ドクトリンと気候変動戦略 |
調査レポート |
ロシアの2030年までのエネルギー戦略 ―その実現可能性と不確実性 |
調査レポート |
メドヴェージェフ政権の環境政策 |
調査レポート |
水道事業から見たロシアの水環境 |
ビジネス最前線 |
ペテルブルグに見るロシアの廃棄物処理事情 |
ビジネス最前線 |
ウクライナビジネスと環境プロジェクト |
エネルギー産業の話題 |
ロシアの白熱電球禁止措置 ―省エネに向けての具体的第一歩 |
自動車産業時評 |
ロシアでエコカーは普及するか |
ドーム・クニーギ |
佐和隆光著『グリーン資本主義』 |
調査レポート |
2009年ロシア乗用車市場の総括 ―激変した環境と新たな商機 |
ビジネス最前線 |
ロシア化粧品市場に「和」の美しさを |
インタビュー |
タジキスタン経済の現状と日本との協力 ―ボボゾダ・タジキスタン新大使に聞く |
研究所長日誌 |
東西冷戦の影響を受けた黎明期の日ソ貿易 |
クレムリン・ウォッチ |
効果挙がるか、メドヴェージェフの警察改革 |
ロシアビジネスQ&A |
◎ロシアの展示会に出展する |
業界トピックス
|
2010年2月の動き ◆ナホトカ市の現在 |
通関統計 |
2010年1月の日本の対ロシア・NIS諸国輸出入通関実績 |
ロシアの気候ドクトリンと気候変動戦略
桜美林大学リベラルアーツ学群 准教授
片山博文
はじめに ―ロシアにおける気候変動戦略の形成
1.気候ドクトリンの概要
2.積極的適応戦略としての気候ドクトリン
3.緩和戦略と排出シナリオ
おわりに ―気候変動の地政学とロシア
はじめに
本論文は、ロシアにおける気候変動政策の転換の意味を考察するため、「ロシア連邦気候ドクトリン」を中心に取り上げ、分析しようとするものである。これはロシア政府による初めてといってよい本格的な気候変動の戦略的文書であるが、この文書は、たんにロシアの気候変動政策の文脈のみならず、気候変動の国際政治全体にとっても注目すべき内容を含んでいるように私には思われる。気候ドクトリンの特徴を一言で言うならば、それは「積極的適応戦略」であるということができる。一般に、気候変動に対処するための方策には、「適応」と「緩和」の2つがある。「適応」とは、すでに起こってしまった気候条件の変化に対処するためにとられる措置のことをいい、また「緩和」とは、温室効果ガスの排出量を削減し、気候変動を抑制するためにとられる措置のことをいう。ロシアの気候ドクトリンは、以下に述べるように、このうち「適応」に比較的大きなウエイトを置き、さらに適応に積極的な意味を賦与している点にその特徴がある。以下本論文では、まず第1節において気候ドクトリンの概要を述べ、次に第2節では、その「適応戦略」としての性格について論ずる。次に第3節では気候ドクトリンの「緩和戦略」としての側面を考察する。そして最後に、気候ドクトリンの有する意味について私見を述べることにしたい。
ロシアの2030年までのエネルギー戦略
―その実現可能性と不確実性―
石油天然ガス・金属鉱物資源機構
本村真澄
1.はじめに ―エネルギー戦略の位置付け
2.エネルギー戦略における石油問題
3.エネルギー戦略における天然ガス問題
4.エネルギー有効利用
5.まとめ
ロシアNIS貿易会と北海道大学スラブ研究センターは、1月20日にTKP東京駅ビジネスセンターにおいて、ワークショップ「ロシアのエネルギー政策とその気候変動政策への影響」を共同で開催いたしました。地球温暖化防止が焦眉の課題となるなかで、エネルギー大国のロシアは、どのような方向に舵をとろうとしているのかという問題意識の下、掘り下げた議論を試みたものです。なお、本ワークショップは、環境省地球環境研究総合推進費H-091「気候変動の国際枠組み交渉に対する主要国の政策決定に関する研究」の助成を受けて開催されました。
ワークショップでは、「ロシアの2030年までのエネルギー戦略:エネルギー利用効率向上との関わり」(本村真澄)、「メドヴェージェフ政権の環境政策:環境ガバナンスの劣化は続くのか」(徳永昌弘)という専門家による2本の報告が披露されました。今般、ご両名に、当日の報告内容をベースとした論文をご寄稿いただきましたので、以下のとおり紹介させていただきます。(編集部)
1.はじめに ―エネルギー戦略の位置付け
「2030年までのエネルギー戦略」が2009年8月27日にロシア政府で採択され、11月13日にロシア政府により承認された。もとより、これは政府のエネルギー政策の方向性を示すだけのもので法的な拘束性はない。ロシアの石油・ガス産業がこの「戦略」に基づいて事業を展開するというものでもなく、これはむしろロシアにおけるエネルギー産業の長期的なピクチャーを提示するものと言える。
メドヴェージェフ政権の環境政策
関西大学商学部 准教授
徳永昌弘
1.ロシアの環境政策
2.メドヴェージェフ政権誕生後の環境政策
おわりに
はじめに
本稿では、現在までに2年近くが経過したメドヴェージェフ政権下の環境政策の内実を探るために、それまでの環境政策の動向を確認した上で、国際的な注目度が高い順に、地球温暖化問題への取り組み、2030年までのエネルギー戦略と省エネルギー法の制定、連邦政府の環境行政機構の再編の3点を考察する。最後にプーチン前政権との相違を念頭に置きながら、メドヴェージェフ政権の環境政策の特徴について検討したい。
水道事業から見たロシアの水環境
富山大学極東地域研究センター 教授
堀江典生
2.ロシアの上下水道
3.ロシアの上下水道管理
4.水資源管理における世界の潮流
5.ロシア版官民パートナーシップは地方を救えるか?
6.取り残される地方
7.ロシアの水資源管理に求められるもの
1.水環境への関心が高まるロシア
近年、ロシアは水問題に真剣に取り組む姿勢を示している。国家プログラム「チースタヤ・ヴァダァ(きれいな水)」が、それを先導することになっている。このプログラムは、2010年に施行される予定となっている。それに合わせて、2009年1月20日にモスクワで国際会議「チースタヤ・ヴァダァ」が開催され、2009年11月24~25日には国際フォーラム「チースタヤ・ヴァダァ」も開催され、ロシア市民の水への関心を高めた。
プログラム草案を提出している統一ロシア党によれば、国家プログラム「チースタヤ・ヴァダァ(きれいな水)」の目的は、飲料水の質の向上と効率化、取水装置の建設・保守、水道の整備、水環境の保全などである。そして、さらに上下水道事業への民間投資を呼び込むビジネス環境を整え、事業への民間事業者の参入を促そうとするものである。上下水道への市場メカニズムの積極的導入、これが成功すれば上下水道事業と同じ問題を抱えるエネルギー供給関連事業へ波及し、ロシアの経済発展に寄与するものと考えられている。それゆえ、このプログラムは、ロシアの公共サービスの効率化をロシア版官民パートナーシップによって推進する試金石といえるプログラムである。
ビジネス最前線
ペテルブルグに見るロシアの廃棄物処理事情
三菱重工業㈱ 機械・鉄構事業本部
機械・鉄構グループ事業推進本部
部長代理 新井俊一さん
部長代理 小島克友さん
はじめに
「ゴミ処理場でもっとも記憶に残るのは臭いです」と新井さんはおっしゃいます。「サンクトペテルブルグでは市民生活からのゴミ処理が大きな問題となっており、市郊外ではまさに風向きによってそのゴミの臭気が感じられるそうです」。日本では昭和46年に首都東京で美濃部東京都知事(当時)が「ごみ戦争」を宣言し、以降現在に至るまで清掃工場の建設加速、ゴミ分別・リサイクル運動等で、官民一体で衛生的な社会インフラを創り上げてきました。他方、サンクトペテルブルグでは社会問題化して約10年間、問題解決が中々進まない様子です。エネルギー・環境という切り口で様々な活動をグローバルに展開している三菱重工を訪問し、世界遺産都市サンクトペテルブルグのゴミ問題の現状と課題についてお聞きしました。
ビジネス最前線
ウクライナビジネスと環境プロジェクト
丸紅㈱ キエフ出張所
所長 松本邦夫さん
はじめに
ウクライナは重厚長大産業を抱え、エネルギー効率が非常に悪い国です。しかし、逆に言えば、環境関連のビジネスチャンスがきわめて大きな国ということにもなります。そのウクライナで、環境ビジネスにパイオニア的に取り組んでおられるのが、丸紅です。炭鉱メタンガスを回収して発電に利用する共同事業(JI)の実績があるほか、日本・ウクライナ間のグリーン投資スキーム(GIS)の案件発掘にも尽力しておられます。そこで、丸紅キエフ出張所をお訪ねし、所長の松本さんにインタビューを試みました。環境だけでなく、ウクライナビジネス全般についても、お話を聞かせいただきました。
なお、本インタビューは12月に実施したものですが、ご存知のとおり、その後ウクライナでは大統領選挙が行われ、ヤヌコーヴィッチ新政権が誕生しました。文中では、インタビュー時のやり取りを活かすため、ユーシチェンコ大統領・ティモシェンコ首相のままとなっています。ただ、読者の皆様は、松本所長が今回の大統領選挙をどのように見たか、お知りになりたいことでしょう。そこで、大統領選挙の結果が出た時点で、松本所長に追加コメントをいただき、記事の末尾に掲載しておりますので、合わせてご参照いただければ幸いです。
エネルギー産業の話題
ロシアの白熱電球禁止措置
―省エネに向けての具体的第一歩―
ロシアでは2009年11月に、省エネに関する連邦法が採択されました。今回は、そのなかでも注目される白熱電球禁止措置の問題を取り上げ、ロシアの一般市民の反応、ロシアの照明器具市場の現状、今後需要が急激に増加すると予測される省エネ照明器具(蛍光灯とLED照明器具)の生産の状況等をご紹介いたします。(坂口泉)
自動車産業時評
ロシアでエコカーは普及するか
ロシアではエコカー(ここではハイブリッドカーと電気自動車のことを指す)はまだ広く一般には認知されていませんが、かなり以前から専門家の間では注目されており、これまで複数の試作品が製作されています(受注生産の段階にまで至った電気自動車もある)。また、最近になり電気自動車量産プロジェクトが発表され大きな話題となりました。
さらに、乗用車市場では富裕層を中心にハイブリッドカーへの関心が、徐々にではありますが、高まりつつあります。
そこで今回は、ロシアの乗用車市場におけるハイブリッドカーのプレゼンスと、ロシアでのエコカーの開発状況等についてご紹介いたします。(坂口泉)
2009年ロシア乗用車市場の総括
―激変した環境と新たな商機―
ロシアNIS経済研究所 次長
坂口泉
はじめに
1.生産動向
2.販売動向
3.経済危機後の国産メーカーの状況
4.主要外資系企業の生産状況
5.ロシア政府の自動車産業支援策
おわりに
はじめに
世界的経済危機の影響を受け、2008年秋頃からロシアの乗用車市場は急激に縮小し始め、いまだ底の見えない状況が続いている。ロシア市場で活動しているすべての自動車メーカーがビジネス環境の急変に戸惑い対応に苦慮しているが、特に純国産メーカーが蒙ったダメージは大きく、その大半が倒産の危機に瀕している。ロシア政府も、もっぱら価格の安さで市場でのプレゼンスを確保するという純国産メーカーのやり方がもはや通用しなくなったことをようやく実感し始めており、今後、同政府が主導する形でロシアの自動車産業の抜本的な改革が試みられる可能性が高まっている。また、ロシア政府は、市場を活性化させるための措置も積極的に実施し始めている。ロシア政府の試みが成功するか否かの判断は難しいが、そこには、外資にとっての大きなビジネスチャンスが見え隠れする。
以上の状況を踏まえ、本稿では2009年の乗用車市場の状況の他、ロシア政府が描いているAvtoVAZ(ヴォルガ自動車工場)とSollersを軸とした自動車産業復興構想、ならびに、同政府が打ち出している市場活性化のための措置を紹介することとする。
ビジネス最前線
ロシア化粧品市場に「和」の美しさを
㈱タウ
執行役員 営業開発部長 藤原央道さん
ウラジオストク オフィス 文後三樹さん
前回、タウさんにご登場いただいたのは本誌2006年1月号です。ダメージカー(事故や故障で壊れたクルマ)のロシア向け輸出で好調な業績を上げておられました。それから4年余り、日ロ貿易を巡る状況が変化するなか、タウさんはダメージカーに続く、新たなロシア市場向け商品として、スキンケア化粧品「MURASAKI」を開発。本誌が出るころにはロシアの店頭に並んでいる予定です。今回は同商品のロシア向けマーケティングに携わってこられた藤原さん、ウラジオストクに駐在し、ロシア人女性へのアンケート調査をされた文後さんより、これまでの経緯やご苦労について伺いました。
Interview
タジキスタン経済の現状と日本との協力
ボボゾダ・タジキスタン新大使に聞く
はじめに
旧ソ連の東南端に位置する小国、タジキスタン共和国の基幹産業は、豊かな水資源を生かした水力発電と、これを利用したアルミニウム精錬、および農業です。独立直後に始まった内戦により経済は大きな打撃を受けましたが、90年代後半から和平プロセスが進行、国際機関との協力のもとで市場化と経済復興への取り組みが開始されました。政情がほぼ安定した2000年以降は、年率10%内外の高い経済成長率を維持しています。
日本との関係では2002年1月に現地日本大使館(駐在官事務所)が、2007年11月に駐日タジキスタン大使館が開設されています。このほど、2代目となるグロムジョン・ボボゾダ大使が赴任されたのを機に、同国の現状をうかがうインタビューを実施しました。
クレムリン・ウォッチ
効果挙がるか、メドヴェージェフの警察改革
昨年末以来、メドヴェージェフ大統領が警察の改革に力を入れ始めました。
昨年11月の大統領教書で、警察の内部粛清を断行する必要性を訴え、12月末には、テレビ生放送の中で、内務省改革の具体的な方針を示しました。放送終了直後に大統領令「内務省機関の活動改善策」に署名するという演出で、熱意を示しました。
この大統領の動きは、直接的には、昨年秋各地で連続的に噴出した警察の不正に関する内部告発を後押しとして利用しています。同時に、警察官による経済犯罪の摘発事例を次々とメディアに流すなど、計画的にバックコーラスを盛り上げた気配があります。(月出皎司)
ロシアビジネスQ&A
ロシアの展示会に出展する
2009年はマイナス成長に陥ったロシア経済ですが、今年に入り回復の兆しが見えており、消費と設備投資の拡大が期待されています。展示会というと、日本や欧米各国ではその退潮が言われて久しいですが、ロシア各地ではさまざまな分野の展示会が頻繁に開催されており、景気回復の期待から展示会への関心が再度高まっています。そこで今回は、ロシアの展示会への出展について、工作機械や農業機械の出展をサポートされたコンサルタントの鐵尾さんにご回答いただきます。