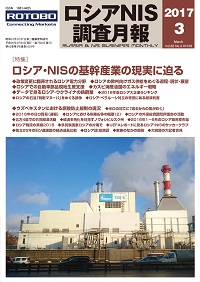 |
|
���V�ANIS��������2017�N�R�������W�����V�A�ENIS�� |
|
���W�����V�A�ENIS�̊�Y�Ƃ̌����ɔ��� |
|
�������|�[�g |
�����ύX�ɖ|�M����郍�V�A�d�͕��� �\2016�N�̓����𒆐S�Ɂ\ |
�������|�[�g |
���V�A�̉��B�����K�X�������߂���ߒ������W�] |
�r�W�l�X�őO�� |
���V�A�ł̎����ԕ��i���n���Y�x�� |
�u���^ |
�J�X�s�C�Y�����̃G�l���M�[�헪 �\�O�I���ω��ւ̑Ή��Ɠ��{�Ƃ̋��͂̉\���\ |
�f�[�^�o���N |
�f�[�^�Ō��郍�V�A�E�E�N���C�i�̓S�|�� �\���E�I�ȋ����ߏ�̒��Ł\ |
�f�[�^�o���N |
2016�N�Ń��V�A���ƃ����L���O |
�G�l���M�[�Y�Ƃ̘b�� |
���V�A�̐Ζ��u�Ő��}�k�[�o�v���߂���_�� |
INSIDE RUSSIA |
���V�A�E�x�����[�V�Η��̔w�i�ɂ���o�ϗ��Q |
�������|�[�g |
�E�Y�x�L�X�^���ɂ����镅�s�h�~�K���̌��� |
�����������z |
�ă��̑Η��Ɂu�ߋ�����̕��������v |
�f�[�^�o���N |
2016�N�̓����f�Ձi����j |
�A�ڃ��|�[�g |
���V�A�ɂ�����Ŗ������̊T�v�i�Q�j |
���X�N���ւ� |
���V�A�̊O����������]�c��̊��� |
���V�A�ɓ����j�� |
�k���S���ł̋����o�ϊ��� |
�n��N���[�Y�A�b�v |
�o�ϑ��p����ڎw���m���H�V�r���X�N�B |
�����ԎY�Ǝ��] |
2016�N�P�`�X���̃��V�A���p�Ԏs�� |
���W�X�e�B�N�X�E�i�r |
���V�A�����̎���2016 |
�f�[�^�̖����� |
���������ƃ��V�A�̕Ћ��� |
�R�������ܘb |
UEFA���|�[�g�Ɍ��郍�V�A�ENIS�̃T�b�J�[�N���u |
�����A�W�A���o�U�[�� |
�Ɨ�25�N�̋��\�A�����̌o�ϐ�����r |
���݈��̃��V�A�� |
�����b |
�V�l�}����ב��I�I |
�Ƒ��̂Ȃ��̌Ǔ� |
�ƊE�g�s�b�N�X |
2017�N�P���̓��� |
�ʊ֓��v |
2016�N�P�`12���̗A�o���ʊ֎��сi����l�j |
�L�҂́u��ʑI���v |
�哝�̂̑�L�҉ |
�������|�[�g
�����ύX�ɖ|�M����郍�V�A�d�͕���
�\2016�N�̓����𒆐S�Ɂ\
���V�ANIS�o�ό������@����������
�����
�@�Ζ����Y�ʂ̋}���ȐL�тƖ����̏㏸�Ƃ����ǂ��������V�A�o�ς�2000�N��ɓ���ɓ]�������A���̊W�œd�͎��v���L�юn�߁A����ɓd�͕s�������O���鐺�����܂��Ă������B���̂悤�ȏ̒��A2005�N�t�ɓd�̓C���t���̘V����������Ƃ�����d�����X�N���Ŗu�����A���V�A���{�͓d�̓C���t���̍��V�Ƒ����ɐ^���Ɏ��g�ݎn�߂��B���d����ł́A�����`���_��ƌĂ��ݔ������̉����ۏ���V�X�e���Ɋ�Â��V���d���j�b�g�̌��݂��ϋɓI�ɍs����悤�ɂȂ����B�܂��A���z�d����ł�RAB�^���t�Ƃ����ݔ�������������l�����������̌n��������ݔ��X�V���ϋɓI�ɍs����悤�ɂȂ����B���̌��ʁA������x�C���t�����߂���͉��P���ꂽ���A�����`���_���RAB�^���t��������������l���������������ݒ��O��Ƃ��Ă��邽�߁A�d�͗��������V�A���{�̑z�������e���|�ŏ㏸����Ƃ������Q�B���̂悤�ȏ��������V�A���{�͕��j����ς����A2013�`2014�N�ȍ~�́A�������i�����d�͗����̗}�����d������悤�ɂȂ��Ă���B���̂��Ƃ͓��R�Ȃ���A�d�͎��Ƃ̗��v���̒ቺ�Ⓤ���ӗ~�̌��ނɂȂ����Ă���A�l�X�Ȗ��݂���B
�@�{�e�ł́A���{�̐����ύX���d�͕���ɂ����炵���e���̑��A�����������Ă���d�͉�Ђ̌���A���{�Œ��ڂ��W�߂���ɓ��n���̓d�͎���A�Đ��\�G�l���M�[���߂���Ȃǂɂ����ڂ��Ȃ���A2016�N�̃��V�A�̓d�͕������ڂ���B
�������|�[�g
���V�A�̉��B�����K�X�������߂���ߒ������W�]
���V�ANIS�o�ό������@������
���J����
�@�E�N���C�i��Ƃ����w�i�Ƃ�����o�ϐ��ق̉e���ɂ��A���V�A��EU�̊Ԃł͌����ȊW�������Ă���A�Ⴆ���V�A����̃G�l���M�[�������߂����ẮA2015�N�Q���ɉ��B�ψ���ł��o�����u�G�l���M�[�����v�헪�Ă��A���B�c��͓�12���Ɋ֘A���錈�c���̑��A���V�A���u�M���ɑ���Ȃ��p�[�g�i�[�v�ƕ]���邱�Ƃ����������B�������A2016�N�A�������������Ɨ����Ƀ��V�A���牢�B�����i�g���R�܂ށj�ւ̓V�R�K�X�A�o�ʂ͉ߋ��ō��̔N��1,793�����Ă��L�^�����B2015�N�Ɣ�r���Ė�12.5���̐L�тł���B�g���R�����A�o�ʂ͑O�N����ł������̂ŁA�L�тɍv�������̂�EU�����̏���Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ��AEU���ōő�̎��v�Ƃł���h�C�c�̗A���ʂ�498�����ĂƂ�������O�N��10���ȏ����K�͂ł������B
�@�������A��N10���ɂ͂T�N�Ԃɂ킽�葈���Ă����K�X�v������EU�����@�ᔽ�ɌW��i�ׁi�����������ɂ����ē��Ђ��D�z�I�n�ʂ𗐗p���Ă���Ƃ̋^�`�j���a�����}���A�K�X�v������OPAL�p�C�v���C���i�Ɩk�������݂Ńm���h�X�g���[���ɐڑ����A�h�C�c��`�F�R�����܂ŃK�X��A���j��A���\�͂̔����܂ł������p���F�߂��Ă��Ȃ��������A���B�ψ����80�`90���܂ł̊��p���������B�������A���̑[�u�ɂ��ẮA���B�ψ���̌���ɕs�����������|�[�����h���c�K�X���PGNiG�����s�̍����~�ߐ��������B�ٔ����Ɏ������݁A��12�����ɓ��ٔ��������̑i���������A�Ƃ����ɂ���A�Z���I�ɂ͂܂��s�����������邱�Ƃ͎����ł���B�������A���B�K�X�s��ɂ�����K�X�v�����̉e���g��������������Ă������B�ψ�����̂悤�Ȕ��f���������Ƃ������Ƃ͏d�����ׂ��ł��낤�B�Ȃ��Ȃ�A���B�ψ���͓V�R�K�X������߂���s�ꃋ�[���̌`�����߂����āA����20�N�߂������V�A���{�A�����ăK�X�v�����Ƌ삯�����𑱂��Ă����̂ł���B�{�e�ł͂��̋삯������U��Ԃ�A���B�����K�X�������߂��鍡��̃��V�A�EU�W�ɂ��ēW�]�����������B
�r�W�l�X�őO��
���V�A�ł̎����ԕ��i���n���Y�x��
�����n�C�e�N�m���W�[�Y���V�A�L�����
�В��@�T�T�쌒����
�@�������n�C�e�N�m���W�[�Y�͏��Ђł�������Y�ƂƁA�������쏊�̌v����O���[�v�E�����̐������u�O���[�v��������2001�N�ɒa��������Ђł��B���[�J�[�@�\�E���Ћ@�\���������ăO���[�o���Ɏ��Ƃ�W�J���Ă���A���V�A�ł͓��n��Ƃ̌��n���Y�x���A�@�B�̕��i��ݔ��̒��B�x���A���V�A�Y�i�̗A�o�Ȃǂ̃r�W�l�X��W�J���Ă��܂��B
�@����́A�����n�C�e�N�m���W�[�Y���V�A�L����ЎВ��̋T�T�삳��ɁA���V�A�ɂ�������n�����ԕ��i���[�J�[�̌��n���Y�x���𒆐S�ɁA���V�A��ƂƂ̃p�[�g�i�[�V�b�v�\�z���ǂ̂悤�ɐi�߂�ꂽ���A���V�A�ɂ����鎩���ԕ��i�s��̌��ʂ��Ȃǂɂ��Ă��b���f���܂����B�i�n粌����Y�j
�u���^
�J�X�s�C�Y�����̃G�l���M�[�헪
�\�O�I���ω��ւ̑Ή��Ɠ��{�Ƃ̋��͂̉\���\
D.�T�g�p�G�t�@A.�A�u�h�D���G�t�@ M.�I�X�p�m�t�@T.�W�����@���B
�@2017�N�P��20���A�J�U�t�X�^���ƃA�[���o�C�W����������Ƃ����ق��A�����̃G�l���M�[�헪�̓W�]�ɂ��ăZ�~�i�[���J�Â����B
�@�J�U�t�X�^���ƃA�[���o�C�W�����͓��{��Ƃ��Ζ��J���ɒ��ڎQ�����Ă��鐢�E�I�ɒ������������ł���B�����̐Ζ��E�K�X�Y�Ƃ���芪�����ɂ́A�Ζ����i�̒�������A��v�f�Ց��荑�ł��郍�V�A�E�����o�ς̑ޒ��A���ݓI�������ł���C�����ɑ���o�ϐ��ى����A�����ɂ���ш�H����̐��i�ȂǁA�l�X�ȕω��������Ă���B�č��̐������A�C�X�����ߌ��h�̑䓪�ɂ�钆����̗������ȂǁA�����I�t�@�N�^�[�̉e�����A���ɐV�K�A���H�̊J��ɂ����Ă͑傫�ȉe�����y�ڂ��B�Ƃ����̂����[���V�A�̐[���Ɉʒu���闼������s��Ɍ�������o����ɂ́A��Ɏ��Ӎ��Ƃ̗��Q�������K�v�ƂȂ邽�߂ł���B
�@������������F���Ɋ�Â��A����̃Z�~�i�[�ł͗����̐Ζ��Y�Ǝ��̂��ނ���A�������芪�����A���Ȃ킿�����̓����A�O���A���ۊW�A�O���������A�Y�Ɛ������ɏœ_�Ă����s��ꂽ�B���{�ł͈��|�I�ɕs�����Ă��闼���̍ŐV����m��M�d�ȋ@��ƂȂ����f��Z�~�i�[�ɂ��āA�ȉ��A�T�v�����Љ��B
�f�[�^�o���N
�f�[�^�Ō��郍�V�A�E�E�N���C�i�̓S�|��
�\���E�I�ȋ����ߏ�̒��Ł\
�@�{���|�[�g�ł́A���E�I�ȓS�|���Y�E�A�o���ł��郍�V�A�ƃE�N���C�i�ɒ��ڂ��A�S�|�Ƃ̍ŐV�f�[�^��}�\�ɂ܂Ƃ߂Ă��͂�����ƂƂ��ɁA��̃f�[�^��������݂�B�i�����ϑ�j
�f�[�^�o���N
2016�N�Ń��V�A���ƃ����L���O
�@���V�A�̌o�ϏT�����w�G�N�X�y���g�x�i2016�N10��24�`30�����ANo.43�j�ɁA���N�P��̃��V�A���ƃ����L���O���f�ڂ���Ă���B���ƃ����L���O�ɂ́A�����̓��W�e�[�}�ł��郍�V�A�̊�Y�Ƃ��\�����Ƃ������o�ꂷ��̂ŁA����͓��W�̈�Ƃ��āA�����L���O�����ďЉ��B�Ȃ��A�{���|�[�g�́u2016�N�Ń��V�A���ƃ����L���O�v�Ɩ��ł��Ă��邪�A2015�N�̔��㍂�ɂ��ƂÂ�2016�N���\�̃����L���O�Ƃ����Ӗ��Ȃ̂ŁA�����ӊ肢�����B
�G�l���M�[�Y�Ƃ̘b��
���V�A�̐Ζ��u�Ő��}�k�[�o�v���߂���_��
�@���V�A���{��2014�N�ɁA�u�i���S���B�E�}�j���[�����i�~�p�|���s���r���z �}�p�~�u�r���j�v�Ə̂���Ζ�����̐Ő����v��ł��o���A���݂��ꂪ���{�i�K�ɂ���܂��B����Ɓu�Ő��}�k�[�o�v�ł���A�P�ɐŗ������肷��Ƃ��������Ƃ����łȂ��A�Ő����e�R�ɐΖ��Y�Ƃ̍\�����v�𐋂��悤�Ƃ���Ӑ}�����߂��Ă��邩�炱���A�u�v���v��u���v���Ӗ�����}�k�[�o�Ƃ������t���p�����Ă���̂��Ǝv���܂��B�{�e�ł́A���V�A�̐Ő��}�k�[�o�̊�{�_��������A���̐����o�ϊw�I�Ȋ܈ӂ�T�邱�Ƃɂ��܂��B�i�����ϑ�j
INSIDE RUSSIA
���V�A�E�x�����[�V�Η��̔w�i�ɂ���o�ϗ��Q
�@2016�N12��26���Ƀ��V�A�̃T���N�g�y�e���u���O�ŁA���V�A�ȂǂT�������琬�郆�[���V�A�o�ϘA���̎�]����J���ꂽ�B�T�~�b�g�̖ڋʂ́A���[���V�A���ʂ̐V���ȊŖ@�T�̒���Z�����j�[�������B�������A�x�����[�V�̃��J�V�F���R�哝�̂͂��̏d�v����{�C�R�b�g�����B�Q���������݁A�x�����[�V�͂��܂��ɊŖ@�T�ɏ������Ă��Ȃ��B���̌�A���V�A�ƃx�����[�V�̑Η����������Ă���A�Q���R���ɂ̓��J�V�F���R�哝�̂��A���[���V�A�o�ϘA�����n�݂���Ă���A�s�����ȉ��i�E�����ɂ��A�x�����[�V��150���h�����̑����������Ɣ�������ꖋ���������B
�@���̂悤�ɁA���V�A�E�x�����[�V�W�͌��������Ă�����̂́A���V�A�E�E�N���C�i�W�̂悤�Ȓn���w�I�ȑΗ��ł͂Ȃ����Ƃɂ͒��ӂ��ׂ����낤�B�x�����[�V�����V�A�ɔ������Ă���̂ɂ́A�؎��Ȍo�ϓI���R������B��̓I�ɂ́A���V�A����̐Ζ��E�K�X�̗A���ƁA�����̎����ԎY�Ƃ̕ی�Ƃ����A�Q�̖��ł���B
�i�����ϑ�j
�������|�[�g
�E�Y�x�L�X�^���ɂ����镅�s�h�~�K���̌���
���z�R�X���@���������@�ٌ�m
����N��
�@�E�Y�x�L�X�^���́A���A�������̒��ŋɂ߂ĕ��s�x�̍������ł���B
�@Transparency International�����{���Ă��镅�s�F���w���ɂ��ƁA�E�Y�x�L�X�^���́A2014�N��175������166�ʁA2015�N��167������153�ʁA2016�N��176������156�ʂł����āA�����A�W�A�����̒��ł͍ł����s�x�̍������Ƃ�������Ă���B�E�Y�x�L�X�^���͍��A���s�h�~�����y���Ă�����̂́AOECD�O�����������d�h�~���͒������Ă��Ȃ��B
�@�����������ŁA���{��Ƃ̓��{��ʋZ�p������Ђ��AJICA��ODA���Ƃł���E�Y�x�L�X�^���S�����Ђ����ǂ���S���d�����ƂɊւ���R���T���^���g�_��̒����A���s���ɂ��ē����Ђ̎҂炩��d�G��v������A2012�N�W�����{�������P�N�Ԃɂ킽��A���v��57��7,000�ăh���i��5,477���~�����j�d���鎖�������������B���̎����́A��Ђ����{�̌��@���Ɏ������Ƃ��_�@�ɔ��o���A�ٔ����̋���������{�ŕs�������h�~�@�ᔽ�ɂ��{����������A�ŏI�I�ɂ́A��Ћy�ь������炪���{�̍ٔ����ŗL�ߔ������A�������ꂽ�B
�@���̂悤�Ȃ��Ƃ��e�����Ă��A�E�Y�x�L�X�^���́A2015�N�W��20���ɌY�@�ƍs���ӔC�@����������������āA���s�K���ɂ��đ啝�ɕύX���A���̓��e�����������̂Ƃ����B
�@�{�e�́A�E�Y�x�L�X�^���ɂ����镅�s�h�~�K���̎�v�Ȃ��̂ł���Y�@�ƍs���ӔC�@�ɂ��Ă̍ŐV�����Љ����̂ł���B
�����������z
�ă��̑Η��Ɂu�ߋ�����̕��������v
�@1990�N��̖����ɂȂ�ƁA���E�e�n�Łu21���I�͂ǂ�Ȑ��I�ɂȂ�̂��v�Ƃ����c�_������ɂȂ�A�u�����̏Փˁv�Ƃ��u�����`�̏I��̎n�܂�v�ƌ������ނ̖{���A�s���ɂ��ǂ܂��悤�ɂȂ�A�E���ƒ�ł��b��ɂȂ�悤�ɂȂ��Ă����B
�@�ă��̑Η��Ɂu�ߋ�����̕��������v�B�����́A�V�����̋}���Ȑ����ƁA�l��������������i�H�ƍ��̐��ނŁA�I���オ�K�R�ƂȂ�Ƃ������R�Ƃ������Ƃ����v�����Ȃ������B������2016�N�ɓ���ƁA6���̉p���̍������[�́uEU����̗��E�v��I�����A���̎葱���ɓ����Ă������B11���ɂ͕č��哝�̑I���ŗ\�z���ċ��a�}�g�����v��₪���I����Ƃ����A�N�V�f���g���N�������B
�@�u���E����������v���O�������ƂȂ��āA�s�����{�����Đ��E���삯���邱�ƂɂȂ�B�i��������j
�A�ڃ��|�[�g
���V�A�ɂ�����Ŗ������̊T�v�i�Q�j
�@���n�����ΏۑI���̎w�j�́A2007�N�T��30���t�A�M�d�ŋǗߑ�MM-3-06/333@���u���n�������x�̃R���Z�v�g�̏��F�ɂ��āv�i�ȉ��A�u���n�������x�R���Z�v�g�j�Ƃ���j�ɒ�߂��A�[�Ŏ҂Ɏ���I�Ɋm�F����悤��������Ă���B�A�M�d�ŋǃT�C�g�ɂ��f�ڂ���Ă���B�Ⴆ�A�ȉ��̂悤�Ȏ������E�ŃX�L�[���̒���Ƃ��āA�����Ώۂ̑I��ɂ����čl�������B�i�������j
���X�N���ւ�
���V�A�̊O����������]�c��̊���
�@���V�A�Ŋ�������O����Ƃ��A���V�A���{�ɑ��Ė���i������I�ȏ�Ƃ��ẮA���V�A�Y�ƉƊ�ƉƘA���iRSPP�j�̍��ۋ��͓����]�c��iICCI�j��Y�Ə��ƏȎ�Â̐V�Y�Ɠ����헪�]�c��Ȃǂ��������݂��邪�A�Ȃ��ł��ł��L�͂ȃv���b�g�t�H�[���ƍl�����Ă���̂��A���V�A����Â���u�O����������]�c��v�ł���B����́A���̊O����������]�c��̊����T�v���Љ�����B�i�����F���j
���V�A�ɓ����j��
�k���S���ł̋����o�ϊ���
�@2016�N12���̓�����]��k�ŁA�k���S���ł̋����o�ϊ����ɂ��āA�S����ΏۂƂ������ʂȐ��x��݂�������n�߂邱�Ƃō��ӂ����B
�@�u���ʂȐ��x�v�Ƃ͉��Ȃ̂��B�܂���̓I�ȃC���[�W�͖��m�ł͂Ȃ��B���x�v�͍���̋��c�Ɉς˂��Ă��邩�炾�B�����|�C���g�Ƃ��ďd�v�Ȃ̂́A���̐��x�����{�ƃ��V�A�̂Q���Ԃł�����Ƃ������Ƃł���B�����č��ۖƂ��Ă���Ƃ��Ă��邱�Ƃł���B���ۖƂ����Ă��A���ꂪ���{�ԋ���Ȃ̂����Ȃ̂��A���ꂩ��̋��c����ł���B�����̂�����̖@�߂ɂ���Â��Ȃ��`�Ƃ��邱�ƂŁA�����̖@�I����Ȃ�Ȃ����x���O���ɂ���B���R�Ƃ����C���[�W�ł����ƁA�o�ϓ���̂悤�Ȍ`���C���[�W���Ă���̂�������Ȃ��B��������������邽�߂ɂ͂܂��A�k���̓y�ɏZ��ł��郍�V�A�l�ɓ��{�Ƌ��͂��邱�Ƃł������Ƃ�����Ǝ������Ă��炤�A�������h���������Ă��炤���Ƃ��O���ɂ���̂��낤�B�i�V�����j
�n��N���[�Y�A�b�v
�o�ϑ��p����ڎw���m���H�V�r���X�N�B
�@�m���H�V�r���X�N�B�́A���X�N���A�T���N�g�y�e���u���O�Ɏ����A���V�A�́u�s�v�Ƃ��đ�R�ʂ̐l�����ւ�m���H�V�r���X�N�s��i����n��ł���B���s�ɂ̓V�x���A�A�M�Nj�̖{�����݂����A�u�V�x���A�̎�s�v�Ƃ��̂����B�Ȃ��A�s���l���͖�156���l�Ƒ傫�����A�B�S�̂ł͖�275���l�ł���A�N���X�m�����X�N�n����C���N�[�c�N�B�Ɠ��K�͂ƂȂ�B���Ό����s�s�̃��f���Ƃ��Ȃ����w�p�������_�u�A�J�f���S���h�N�v�����邱�ƂŒm���Ă���n��ł���A38�̉Ȋw�A�J�f�~�[�x���⌤���@�ցA�v���������J���E�����ɏ]�����A�܂���w�Ȃ�50���鋳��@�ւ��W�ς��A13���l�߂��̊w�����l�X�ȋ���v���O���������Ă���B�������A���B�̌o�Ϗ�Y�Ƃɂ��Ă͓��{�ł͂قƂ�ǒm���Ă��Ȃ��ƌ����Ă������낤�B
�@�����ŁA�{�e�ł́A�y�ъe�팤�������ɉ����A�B���{�⓯�B�������W�G�[�W�F���V�[��������������Q�l�ɁA���B�̌o�ρE�����T���A�����Č��Ȃǂ��Љ�����B�i���J���Ɓj
�����ԎY�Ǝ��]
2016�N�P�`�X���̃��V�A���p�Ԏs��
�@���V�A�̒�����ЁuASM�z�[���f�B���O�v���A2016�N1�`�X�����̃��V�A�̏��p�ԁi�g���b�N�A�o�X�A���^���p�ԁj�̐��Y�A�̔��A�A���Ɋւ���f�[�^����肷�邱�Ƃ��ł��܂����̂ŁA����́A�����̃f�[�^�����Ƃɓ����̃��V�A�̏��p�Ԏs��̏����Љ�邱�Ƃɂ��܂��B�i�����j
���W�X�e�B�N�X�E�i�r
���V�A�����̎���2016
�@��������A�������o�ϐ��قȂǂ̋t�����ŕs���ɋꂵ��ł������V�A�o�ςł����A2016�N�㔼�ɂȂ��Čo�ς͒��ł����ƌ����܂��B�����̕���ł͂ǂ��������̂ł��傤���B�`�p�A�S�������̑���l����ɐU��Ԃ�܂��B�i�ҋv�q�j
�f�[�^�̖�����
���������ƃ��V�A�̕Ћ���
�@���V�A�͑��������Ƃł���B�\�A�����݂�������A15�̋��a��������A���V�A�l�̊����͔������x���߂Ă������A�\�A��̂ŐV�����V�A���a�����A���V�A�F�����ɋ��܂�A��W�������V�A�l�ƂȂ����B
�@����́A���W���[�Ȗ����̘b�ł͂Ȃ��}�C�i�[�Șb�����S�ł���B���V�A�̖����̐��͂ǂ̒��x����̂��낤���B2010�N�̍��������̖����\�����݂�ƁA146�����𐔂��邱�Ƃ��ł��邪�A���̂���21�����ɂ��ĉ��ʂ̖����O���[�v������A�������ƌ����\��������A48�ƂȂ��Ă���B���Ȃ݂ɁA���V�A�l�ɂ��Q�����������݂���B�ЂƂ́A�L���ȃR�T�b�N�A�����ЂƂ͕M�҂��S���m��Ȃ������|���[���ł���B���������P���ɉ������194�Ƃ������ƂɂȂ�B���V�A�̖����̐��͖�150�A���邢�͖�200�Ƃ������Ƃňꉞ�A�ԈႢ�͂Ȃ��̂��낤�B�i�����_�j
�R�������ܘb
UEFA���|�[�g�Ɍ��郍�V�A�ENIS�̃T�b�J�[�N���u
�@���B�T�b�J�[�A���iUEFA�j�͍��ʁAUEFA����54�����̃T�b�J�[�N���u��2015�N�x�̎��т��������|�[�g�\�����iThe European Club Footballing Landscape: Club Licensing Benchmarking Report: Financial Year 2015�j�B�ȉ��ł͂��̒�����A���V�A�ENIS�����̃T�b�J�[����ɂ������̂���_�����ďЉ��B�i�����ϑ�j
�����A�W�A���o�U�[��
�Ɨ�25�N�̋��\�A�����̌o�ϐ�����r
�@�J�U�t�X�^���̐�厏�w�G�N�X�y���g�E�J�U�t�X�^���x��2016�N12���T��No.23���œ����̓Ɨ�����25�N�̌o�ρA�����A�ΊO�������ɂ��đ�������L�����f�ڂ����B���̒��̌o�ςɂ��Č��y���Ă��镔���ŁA���E��s�̃f�[�^�Ɋ�Â��A���\�A������GDP�A�o�ϐ������̕ω��Ȃǂ��r�����f�[�^��������Ă���A�Ȃ��Ȃ������[���B�����ŁA�{�e�ł͓��L���ŏЉ�ꂽ�f�[�^���ȒP�ȉ���ƂƂ��ɂ��Љ�����B
�@�Ȃ��A�����ł͐��E��s�̃f�[�^�Ɋ�Â��ăO���t���쐬����Ă��邪�A��̓I�Ȑ��l���L�ڂ���Ă��Ȃ��B���������āA�O���t�̍쐬�ɂ������āA���߂Đ��E��s�̃f�[�^���m�F�����Ƃ���A�ꕔ�̃f�[�^�ɂ��Ċm�F�����Ȃ��������Ƃ�����A�O���t�͓Ǝ��ɍ쐬�������߁A�L���Ƃ͎�قȂ�_�ɂ����ӂ������������B�i���n���M�j
���݈��̃��V�A��
�����b
�@���V�A�ɒ��݂�����{�l�́A���{�Ŏx�����鍑�����i�~���āj�̂ق��Ɍ��n�Ń��[�u�����Ă̋��^��������Ă���͂����B�~�E���[�u���̊����͉�Ђɂ���ĈႤ���낤���A���Ȃ�̊z�����n��Ђ��烋�[�u���Ŏx�����Ă���ɈႢ�Ȃ��B�ł��茘���l�� ���[�u�������ɋ��^���U�荞�܂��₷���ɕăh���ɑւ��A�X�ɂ��ꂾ���ł͈��S�ł��Ȃ̂ŁA����1�x�̃y�[�X�œ��{�ɑ������� �B����A���ڒ��Ȑl�͕��ʌ����ɗ��܂��Ă������[�u�������̂܂܂ɂ��A�A�C���O�ɕăh���ɑւ��ē��{�ɑ�������B ����ȂȂ��Ń��V�A�ɂ��邱�Ƃ𗘗p���A�����I�ɂł������𓊎��ɉl������̂ł͂Ȃ��낤���B���̐l�̃t�B�i���V�������e���V�[ ��X�N���e�x�Ƃ������A�T�d�Ȃ̂��A�t�ɑ�_���A�������������œ���������낢��ł���B�܂��ɏ\�l�\�F�����炾�B�i�V�䎠�j
�V�l�}����ב��I�I
�Ƒ��̂Ȃ��̌Ǔ�
�w���F���̋F��xVS�w�G���i�̘f���x
�@���N�������ȏt�̍���ƁA�`���[���b�v�≩�F�̃~���U�̉Ԃ����������ɔ����A�s���ەw�l�f�[�t�̖K�ꂪ�������鎞�߂ƂȂ�܂����B����Ȏ��ɂ����ӏ܂������̂��A������_��̑��݂Ɛ��߁A���̐S���̓������߂����܂܂ɕ`�o����V���ȏ����f��̐V���n���J�����A���h���C�E�Y�r���M���c�F�t�̂Q�̍�i�ł��B�Y�r���M���c�F�t�ƌ����A�w���A�A��x(�B���x�r���p���u�~�y�u)�ŕ��e�Ƃ�����̑��݁A���E���̃e�[�}���捂ɂ��Ď�������f���ɂ܂Ƃ߁A2004�N�A�f�r���[��ɂ��ă��F�l�c�B�A���ۉf��ՁE�����q�܂����������܂��Ă��܂����V�˂ƌ����Ă悢�ēł����A�v���b�V���[�Ƃ͖����̂悤�ŁA���������A��Ɛ������łȂ��̂Ƃ��A���̂��т��Љ��Q�̍�i�ƁA�����Ă�͂�A���ۓI�ɍ����]�����S�[���f���E�O���[�u�܂�J���k���ۉf��ՂŎ�܂�������w�ق����͑P�l�̂݁x(�L�u�r�y�p���p�~/2014)���R���X�^���g�ɐ��ɑ���o���Ă���܂��B���̂悤�ȓV�˂Ɠ�����ɐ����ނ̍�i���ӂ邱�Ƃ��ł���͙̂F��Ƃ���������܂���B
�@�b��́A�����f��ł����B�܂��́A�w���F���̋F��x���炲�Љ�܂��傤�B�i������o���j
�L�҂́u��ʑI���v
�哝�̂̑�L�҉
�@�N���̃��V�A�����Ƃ����ΊX�p�̃��[���J�A�f��u�^���̔���v�A�o���G�u����݊���l�`�v�A�����ăv�[�`���哝�̂����O��1000�l���̋L�҂������čs����K�͂ȋL�҉�ł���B���ƌ���Ɏ��R�Ɏ���ł��A�������͂S���Ԕ��ȏ㑱�����^�����́A���E���Ń��V�A�ɂ����Ȃ��B�Ƃ������A�v�[�`�����ɂ����ł��Ȃ����낤�B�ނ��哝�̂ɕ��A����2012�N�ȍ~�A12���J�Â��P��ɂȂ����B�i���F�G���j









