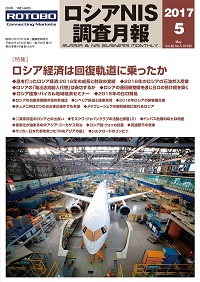 |
|
ロシアNIS調査月報2017年5月号特集◆ロシア経済は |
|
特集◆ロシア経済は回復軌道に乗ったか |
|
調査レポート |
底を打ったロシア経済: 2016年の成長と財政の実績 |
調査レポート |
2016年のロシアの石油ガス産業 ―油価の低迷というキーワードを軸に― |
調査レポート |
ロシアの「輸出志向輸入代替」は奏功するか |
ビジネス最前線 |
ロシアの通信網整備を通じ日ロの懸け橋を築く |
講演録 |
ロシア極東・バイカル地域経済セミナー |
データバンク |
2016年の日ロ貿易 ―石油ガス輸入の落ち込みが響く― |
自動車産業時評 |
ロシアの自動車整備市場の新潮流 |
ロジスティクス・ナビ |
シベリア鉄道と極東港湾 |
産業・技術トレンド |
2016年ロシアの旅客機生産 |
地域クローズアップ |
チュメニ州は2つの自治管区抜きでも有望 |
INSIDE RUSSIA |
メドヴェージェフの腐敗疑惑に揺れるロシア |
研究所長随想 |
二葉亭四迷のロシアとの出会い |
モスクワ便り |
モスクワ・ジャパンクラブの活動と課題(2) |
ウクライナ情報交差点 |
ドンバス危機の新たな局面 |
中央アジア情報バザール |
家族化が強まる中央アジア・コーカサス政治 |
駐在員のロシア語 |
ウォッカ談義 |
シネマ見比べ隊!! |
英雄都市の表象 |
蹴球よもやま話 |
サッカー日本代表を救った「中央アジアの笛」 |
業界トピックス |
2017年3月の動き |
通関統計 |
2017年1〜2月の輸出入通関実績 |
記者の「取写選択」 |
シルクロードのコンビニ |
調査レポート
底を打ったロシア経済:2016年の成長と財政の実績
北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター 教授
田畑伸一郎
ロシア経済は、2015年からマイナス成長となっていたが、2016年にはGDPの下げ幅が0.2%となり、底を打ったと見られる。四半期別の統計を見ると、2016年第4四半期には、GDPは対前年同期比0.3%の増加となっている。これには、油価の低下が底を打ったことが寄与している。GDPを生産部門別に見ると、2015年に4.6%減少した製造業において、2016年には1.1%の増加となったことが象徴的である。GDPを支出項目別に見た場合には、2015年に9.9%減少した総固定資本形成の減少が2016年には1.8%の減少になっている。2016年における経済の大きな改善点は、2014年から2年続けて10%を超えていたインフレ率が5.4%にまで下がったことである。これは、油価の底打ちとともに、ルーブル・レートの低下が止まったことによるところが大きかった。2016年には油価が緩やかに上昇したことから、株価も回復傾向にある。このように、ロシア経済は様々な点で2014〜2015年よりはかなり良い状況になったと言える。しかしながら、油価は依然として低い水準にあり、家計の所得や消費、商業などの改善はまだまだである。油価の低迷は、対外経済関係の改善を遅らせており、財政の面でも深刻な状況が続いている。そのようななかで、ロシア経済が石油・ガス依存から脱却するような兆しもあまり見えていない。投資における若干の回復傾向は、ヤマルLNGプロジェクトによるところが大きく、輸入代替による生産拡大の勢いはまだ弱い。
調査レポート
2016年のロシアの石油ガス産業
―油価の低迷というキーワードを軸に―
ロシアNIS経済研究所 嘱託研究員
坂口泉
2016年も油価の下落傾向が続き、ロシアの主要油種であるUralsの輸出価格の平均値はバレル42ドルにとどまった。ロシアの石油分野の主要な税金である採掘税と輸出関税はいずれも累進性を有しており、一説によれば、西シベリアの平均的な石油鉱床の場合、油価がバレル50ドルの時には売上高に占める納税額の割合が6割強であるのに対し、100ドルを超えると75%以上に達するともいわれている。これは、裏を返せば、油価が上昇すると国の税収が加速度的に増加するが、逆の場合は加速度的に減少するということを意味し、2014年秋頃から続く油価の下落傾向はロシアの国家予算に想像以上のダメージを与えていると考えてよいであろう。一方、石油会社も当然ダメージを受けているが、油価の下落に伴い採掘税と輸出関税の負担が軽減されるので、国と比較するとまだ余裕があるといえよう。2016年も前年に引き続き石油ガス分野に対する政府の課税圧力強化の動きが目立ったが、おそらく、そこには「油価の低迷で石油ガス会社も厳しいのは理解できるが、それよりももっと国家財政は厳しいので石油ガス分野には我慢してもらいたい」という発想が存在するものと推測される。その他、油価の低迷に伴う国家財政の危機的状況は、バシネフチとロスネフチという2つの国営石油会社の強引な民営化を促す温床ともなった。さらに、油価の低迷の影響はガス分野にも飛び火し、ガスプロムのガスの輸出価格の低下という現象も生んだ。
本稿では、油価の低迷というキーワードを意識しながら、2016年のロシアの石油ガス分野を回顧する。
調査レポート
ロシアの「輸出志向輸入代替」は奏功するか
ロシアNIS経済研究所 調査部長
服部倫卓
過去2〜3年ほど、ロシアで経済政策の最重要なキーワードの一つとなってきたのが、「輸入代替」である。筆者はちょうど2年前に「輸入代替に賭けるロシア」と題するレポートを発表し、ロシアの輸入代替をめぐる状況と政策展開について論じた。
本稿では、2年前のレポートで論じた基本点を再確認するとともに、その後の輸入代替の進捗状況を、図表を用いながら概観する。また、最近のロシアでは「輸出志向輸入代替」という標語が掲げられるようにもなっているので、その点にも触れてみたい。
ビジネス最前線
ロシアの通信網整備を通じ日ロの懸け橋を築く
NEC NEVA Communications Systems 社長
桜井明博さん
1980年のモスクワ五輪の映像を世界に配信した衛星地上局の納入をはじめ、NECはロシア・ビジネスに長い経験を有しています。ソ連解体後は、日ロハイテク合弁第1号であるNEC NEVA(ネヴァ)を設立し、デジタル電子交換機の生産を行いました。また近年では、モバイル通信の基地局間を接続するシステムの供給とサービス化に力を入れるなど、NECはロシアの通信網構築に大きな貢献をしています。こうした点を含めて、今回は、NEC NEVA Communications Systemsの桜井明博社長にお話を伺いました。(中居孝文)
講演録
ロシア極東・バイカル地域経済セミナー
P.ミナキル N.スィソエヴァ
ロシアNIS貿易会では3月8日、10日に、東京および札幌において、ロシアを代表するエコノミストで、ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所博士のパーヴェル・ミナキル氏と、イルクーツク研究センター博士のナターリア・スィソエヴァ氏を講師に招き、「ロシア極東・バイカル地域経済セミナー」と題する講演会を開催した。
ミナキル氏より「ロシア極東の経済:現状と展望」、スィソエヴァ氏より「ロシアイルクーツク州およびバイカル地域の経済発展の現状と展望」という題で報告がなされた。以下ではその内容を抜粋してご紹介する。
データバンク
2016年の日ロ貿易
―石油ガス輸入の落ち込みが響く―
例年どおり、日本財務省の貿易統計にもとづいて、2016年の日本とロシアの貿易に関し、データをとりまとめて紹介する。当会ではすでに、『ロシアNIS経済速報』2017年2月5日号(No.1717)において、2016年の日ロ貿易を速報値で紹介済みだが、本レポートでは確定値を掲載する。(服部倫卓)
自動車産業時評
ロシアの自動車整備市場の新潮流
景気の低迷は自動車整備市場にも影響を及ぼすようになっており、整備保証期間が過ぎると車の修理や整備をディーラーではなく独立系の整備工場に依頼するユーザーの数が以前よりもさらに増加しています。その関係もあり、フランチャイズ方式で整備工場のチェーン展開を試みる会社の数が増加傾向にあります。一方、ディーラーの方はそのような独立系整備工場の攻勢に対抗するため、純正部品の価格の値下げを自動車メーカー側に要求するなどの措置を講じています。以上の状況を踏まえ、本稿では、整備工場のチェーン展開をしている3つの会社の動きをご紹介することにします。 (坂口泉)
ロジスティクス・ナビ
シベリア鉄道と極東港湾
シベリア鉄道と極東港湾は一体となって、内陸部に産出する資源品や工業品のアジア諸国向け輸出に貢献しています。ルーブル安を背景に、賑わう大陸鉄道と極東港湾の動向を紹介します。(辻久子)
産業・技術トレンド
2016年ロシアの旅客機生産
ロシアの旅客機生産はソ連崩壊後しばらく停滞していたが、2010年以降にスホーイスーパージェット(以下SSJ)の量産が立ち上がり、2014年まで急速に回復していった。しかし、2015年にSSJの生産が半減し、これまでの勢いを失った。2016年の旅客機生産はSSJが1機増えたのみで、その他機種も微増したため、合計で3機増にとどまり、2015年と比べ実質的には横ばいであった。一方で、新型旅客機MC-21の開発が進み、6月にロールアウト式典がなされた。よほどのことがない限り、2017年には初飛行する。一見すると、2016年の旅客機生産は代わり映えしないものに見えるが、将来が期待できる新機種の開発が着実に進んでいるためロシアの航空産業としては、前進のあった重要な年であった。
今回は2016年のロシアの旅客機生産の状況について紹介する。なお、生産数はロシアの航空業界誌であるVzlyot誌上の数値を使用している。
(渡邊光太郎)
地域クローズアップ
チュメニ州は2つの自治管区抜きでも有望
ロシア経済を支える石油・ガス産業。伝統的にその中心は西シベリア地域であり、そこには世界有数の油田地帯として知られるチュメニ油田がある。その油田の名前と同じ名称を持つのが本稿で紹介するチュメニ州だ。しかし、チュメニ油田群で豊富な産出量を誇る大規模な鉱区のほとんどはチュメニ州からは実質的に独立した連邦構成主体であるハンティ・マンシ自治管区とヤマロ・ネネツ自治管区に広がっている。そのため、ロシア最大の石油およびガス生産量を誇る両自治管区を除いたチュメニ州本体となると、有力な石油・ガスの産出地域とは言いがたい。本稿では、2つの自治管区の陰に隠れがちだが、様々なポテンシャルを有し、地域住民がその質を誇るチュメニ州について紹介する。(中馬瑞貴)
INSIDE RUSSIA
メドヴェージェフの腐敗疑惑に揺れるロシア
ロシアでは3月2日に、反体制ブロガーのアレクセイ・ナヴァリヌィ氏が、メドヴェージェフ首相の重大な蓄財疑惑を暴露する動画を公開した。それが発端となって、ロシア全土に反体制デモのうねりが広がり、3月26日には全国約100の都市で同時多発的にデモが開催された。うち当局の許可を得ていたものは21だけだったと言われているが、無許可にもかかわらず、モスクワでは少なくとも1.5万人が、サンクトペテルブルグでも1万人が集まるなど、予想外の広がりを見せた。今回特徴的だったのは、既成の野党勢力はほとんど組織に関与していなかったこと、デモ参加者に十代、二十代の若者が圧倒的に多かったことである。(服部倫卓)
研究所長随想
二葉亭四迷のロシアとの出会い
二葉亭四迷(本名 長谷川辰之助)は、1864年2月江戸市ヶ谷合羽坂にあった尾張藩上屋敷で、尾張藩士長谷川吉数の一人息子として生まれた。二葉亭四迷が生きた時代は、日本が近代国家へと生まれ変わる動乱期であった。4歳の時、諸藩の江戸屋敷は引き払いとなり、二葉亭一家は父を江戸に残し、郷里の名古屋に引き上げることになった。(遠藤寿一)
モスクワ便り
モスクワ・ジャパンクラブの活動と課題(2)
日本企業が多く活動している国・都市には、日本企業同士の親睦や情報交換等を目的とした商工会組織が存在し、モスクワではモスクワ・ジャパンクラブがそれにあたる。前号では、モスクワ・ジャパンクラブの歴史と組織、そして活動内容を紹介したが、今回は同クラブの今後の課題について思うところを述べてみたい。(中居孝文)
ウクライナ情報交差点
ドンバス危機の新たな局面
ウクライナでドンバス紛争が発生してから、3年間が経過した。東ウクライナ・ドンバス地方のドネツィク(ドネツク)州およびルハンシク(ルガンスク)州で、ウクライナ中央政府の路線に異を唱える分離主義武装勢力が、ロシアの支援を受けつつ、両州の相当部分を占領・支配し、「ドネツィク人民共和国」、「ルハンシク人民共和国」の樹立を自称しているものである。最新の情報によれば、2014年4月半ばから続くドンバス紛争では、政府軍と武装勢力の衝突で、少なくとも9,940人の死者、2万3,455人の負傷者が出ているということである。(服部倫卓)
中央アジア情報バザール
家族化が強まる中央アジア・コーカサス政治
以前、本連載において、中央アジア諸国の大統領を親に持つ各国の有力な二世エリートたちを紹介した(『ロシアNIS調査月報』2015年11月号)。あれから約1年半が経過し、最近、再び一部の中央アジア・コーカサス諸国において大統領の有力な後継者候補とも考えられる家族の政界での動向が注目されている。(中馬瑞貴)
駐在員のロシア語
ウォッカ談義
ウォッカって一体どうやってつくるの? と酒を飲みながら日本人駐在員の間で話題になることもあるだろう。答えは至極簡単だ。ちょっと前に流行った○○太郎風に言えば 「アイハヴ ウォーター、アイハヴ エタノール、ハーン、ラッシャーン ウォッカ!」つまり約96%の精留エチルアルコール(エタノール)を度数40°になるように水で希釈してつくったもの。これほど混じり気のない純度の高いメタノールをベースにしたアルコール飲料の製法は世界で唯一なのだ。以上で終わり!いやいやこれで終わりなら、だれでもエタノール(未変性のもの)を入手し、精留水で薄めればできてしまう。本来どのように作られているのかを歴史も含め見てみることにする。(新井滋)
シネマ見比べ隊!!
英雄都市の表象
5月のこのコーナーで、ロシアの対独戦勝記念日(5月9日)に因んで2本の戦争映画をご紹介するのはこれで3度目となります。戦後から今日まで、ソ連・ロシアでは独ソ戦を扱った戦争映画が実に多く制作されてきたわけですが、このたびは、レニングラード包囲戦をテーマとした2つの作品をご紹介しましょう。レニングラード包囲戦といえば、1973年から1977年にかけ撮影された全編6時間を超える超大作『レニングラード攻防戦』(ミハイル・エルショフ監督)を挙げないわけにはいきませんが、今回は、この『攻防戦』を踏まえつつ、レニングラード包囲戦を新たな観点から描出している1985年と2007年の映画におけるレニングラード封鎖をみていくことにしたいのです。まずは、2007年に制作されたより新しい「レニングラード包囲戦」から。(佐藤千登勢)
蹴球よもやま話
サッカー日本代表を救った「中央アジアの笛」
スポーツ界には、「中東の笛」という言葉がある。国際的なスポーツ大会において、試合日程や審判のジャッジがアラブ諸国に有利になる現象のことを指す。特に、クウェートの王族がアジア連盟を牛耳っているハンドボールでその現象が顕著であり、過去にはオリンピック出場権をかけたアジア予選で中東の笛が吹き荒れ、物議を醸したことがあった。
サッカーでも、それを彷彿とさせるような出来事が起きた。(服部倫卓)
記者の「取写選択」
シルクロードのコンビニ
カザフスタンの商都アルマトイに2013年1月、旧ソ連初の日本のコンビニ「ミニストップ」が進出した。レジの脇にホカホカの肉まんやチキン唐揚げ。棚には三角おにぎりやスイーツ。軽食の品質は日本に比べると劣るとはいえ、まさにシルクロードのオアシス。アルマトイ出張が俄然楽しくなった。(小熊宏尚)









