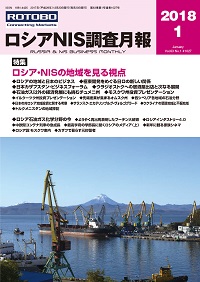 |
|
ロシアNIS調査月報2018年1月号特集◆ロシア・NISの |
|
特集◆ロシア・NISの地域を見る視点 |
|
調査レポート |
ロシアの地域と日本のビジネス |
調査レポート |
極東開発をめぐる日ロの新しい関係 |
イベント・レポート |
日本カザフスタン・ビジネスフォーラム ―カザフスタンの投資政策と地方における投資機会― |
ビジネス最前線 |
ウラジオストクへの居酒屋出店と次なる展開 |
ミニ・レポート |
石油ガス以外の経済発展にも挑むチュメニ州 |
イベント・レポート |
モスクワ州投資プレゼンテーション |
イベント・レポート |
イルクーツク州投資プレゼンテーション |
ミニ・レポート |
先端産業が集まるオムスク州 ―シベリアの「ウラル」?― |
エネルギー産業の話題 |
西シベリア各地域の石油分野 |
ロシアと日本・ 出会いの風景 |
日本の対ロシア地域投資に関する考察 |
蹴球よもやま話 |
サランスク・エカテリンブルグ・ヴォルゴグラード ―サッカー日本代表三都物語― |
ウクライナ情報交差点 |
ウクライナの堅調地域と不振地域 |
中央アジア情報バザール |
トルクメニスタンの地域探訪 |
調査レポート |
ロシア石油ガス化学分野の今 ―新プロジェクト停滞の背景― |
INSIDE RUSSIA |
ようやく再出馬表明したプーチン大統領 |
デジタルITラボ |
ロシアインダストリー4.0 |
ロジスティクス・ナビ |
中欧間コンテナ列車の急成長 |
ロシアメディア最新事情 |
最高学府の学部長に聞くロシアのメディア(上) |
シネマ見比べ隊!! |
新年に観る家族シネマ |
駐在員のロシア語 |
モスクワ案内:赤の広場編 |
業界トピックス |
2017年11月の動き |
通関統計 |
2017年1~10月の輸出入通関実績 |
記者の「取写選択」 |
カザフで暮らす元抑留者 |
調査レポート
ロシアの地域と日本のビジネス
ロシアNIS経済研究所 調査部長
中居孝文
本誌で詳しく紹介するように、この秋、当会ではタタルスタン共和国(10月2日)、イルクーツク州(11月9日)、モスクワ州(11月21日)の投資プレゼンテーションを立て続けに開催した。その他の地域からも日本でプレゼンテーションを行いたいという提案をいくつか受けており、当会としてはその要望にできるだけ応えるべく前向きに検討しているところである。
周知のとおり、昨年来、日ロ両国首脳の強いイニシアチブにより、両国政府間の対話が頻繁に行われ、それにともない両国のビジネスも拡大していくのではないかとの期待が高まっている。ロシア各地の行政府からのアプローチの増加は、今後、日本企業のロシアへの進出が増えてくるという期待感の現れなのかもしれない。
本稿では、ロシアの地域が有する基本的特性、ロシアにおける日本企業の地域別の進出状況、そしてロシアの各地域による日本のビジネスへのアプローチや日ロ間の認識のギャップ等について概観したい。
なお、本稿では、「日本企業の進出」という表現がたびたび出てくるが、その場合の「進出」とは「現地法人の設立」という意味で使用していると理解していただきたい。
調査レポート
極東開発をめぐる日ロの新しい関係
ロシアNIS貿易会モスクワ事務所 所長
齋藤大輔
かつてロシア極東は、ロシアの最果ての地だった。ロシア人にとっても、日本人にとっても、あえて行きたいとは思わない場所であった。
プーチン政権は、アジア重視を掲げ、極東地域のインフラ整備や投資誘致に取り組んできた。それは、立ち遅れたこの地域を変えようとする苦悩の表れでもあり、この場所を利用して、アジア太平洋諸国との政治経済関係を強化しようとする老獪な戦略でもあった。
そんな中、日ロ関係拡大の機運から、新しい日本企業が極東地域に進出し、存在感を高めている。極東地域との関係発展は、安倍政権が掲げる対ロ経済協力「8項目の協力プラン」の1つともなっている。なぜいまロシア極東なのか。
そこで本稿は、最初に日本とロシア極東の経済ビジネス動向、新型特区やウラジオストク自由港などプーチン政権が挑む極東政策の最新動向を紹介して、最後にロシアは極東をどうしたいのか、日本にとってのロシア極東は何かについて考えてみる。
イベント・レポート
日本カザフスタン・ビジネスフォーラム
―カザフスタンの投資政策と地方における投資機会―
2017年10月31日、東京のホテル・ニューオータニにて、ロシアNIS貿易会、日本カザフスタン経済委員会、在日カザフスタン共和国大使館、国営企業「カザフインベスト」が主催する日本カザフスタン・ビジネスフォーラム「カザフスタンの投資政策と地方における投資機会」が開催されました。
今回のフォーラムには、日本とのビジネス拡大を目的に、カザフスタンより中央・地域行政府の代表、投資誘致機関、民間企業等からなる総勢80名にものぼる大代表団が来日、一方、日本側からも約180名の関係者が参加しました。
現在、カザフスタンでは、今回の主催者のひとつである投資誘致機関「カザフインベスト」の新設をはじめ、投資政策の大転換が進められており、諸地域への外国投資誘致もそのうちのひとつの柱となっています。その表れとして今回のフォーラムには、全国16の地域行政府のうち11の州・特別都市より副知事クラスが参加、日本側へ投資誘致を呼びかけました。
以下、日本カザフスタン・ビジネスフォーラムの概要についてご報告致します。(輪島実樹・片岡久美子)
ビジネス最前線
ウラジオストクへの居酒屋出店と次なる展開
㈱伸和ホールディングス 代表取締役社長
佐々木稔之さん
ウラジオストクで2017年4月に日本流の居酒屋を開いたのが、札幌市に本社を構える外食チェーンの伸和ホールディングスです。店は日ロ双方のマスメディアにも取り上げられ、9月に開かれた東方経済フォーラムでは佐々木稔之代表取締役社長が日本の中小企業を代表してスピーチを披露しました。海外進出未経験だった同社がロシアに進出した経緯や、店の業績、今後の展開などについて佐々木社長に伺いました。(吉村慎司)
ミニ・レポート
石油ガス以外の経済発展にも挑むチュメニ州
ハンティ・マンシ、ヤマロ・ネネツ、トボリスクと挙げていくと、ロシア通の人は共通項が石油とガスだと気づくだろう。チュメニ州で1960年代に始まった資源開発は、需要拡大に伴って国内だけでなくヨーロッパにも輸出されるようになり、ロシア最大の生産地帯に成長した。その経済規模は首都のモスクワ市に次ぐまでになった。
そんなチュメニ州だが、日本ではあまり知られていない。2017年10月、ロシア工業団地協会主催「チュメニ州視察会」にロシアや欧米企業の代表者とともに参加した。そこで本稿では州の概要、そこで活動する企業、さらには同州の投資誘致活動について報告する。まずは州の概要を紹介する。(齋藤大輔)
イベント・レポート
モスクワ州投資プレゼンテーション
2017年11月21日、ヴォロビヨフ知事を団長とするモスクワ州代表団の訪日を機に東京・ホテルニューオータニにてロシアNIS貿易会とモスクワ州政府の共催による「モスクワ州投資プレゼンテーション:Make with Moscow Region」が開催され、ロシア側からはモスクワ州の関係者約30名、日本側からは当会会員を中心に約120名が参加した。
モスクワ州では、同州への外国企業の誘致のために、州政府及び企業の代表からなるミッションを「ロードショー」と称して各国へ派遣している。例えば、2017年には、これまでイタリア、ドイツ、フィンランド、フランスでロードショーを実施しており、今回はその一環としてアジアで初めて日本と韓国においてロードショーを開催した。
今回の日本でのロードショーにおいては、標題のプレゼンテーションを当会と共催で開催したほか、ヴォロビヨフ知事による世耕弘成経済産業大臣への表敬、日野自動車の羽村工場訪問、墨田清掃工場の視察等が行われた。そのうち本稿では、「モスクワ州投資プレゼンテーション:Make with Moscow Region」の概要を紹介することとする。(中居孝文)
イベント・レポート
イルクーツク州投資プレゼンテーション
レフチェンコ・イルクーツク州知事を団長とする代表団の訪日の機会に、2017年11月9日、東京で「イルクーツク州投資プレゼンテーション」を開催した。同州からは約20の企業・団体の代表者が参加し、日ロ合わせると130名以上が本プレゼンテーションに参加した。プレゼンテーション終了後、約20件の個別商談が組織されたほか、イルクーツク州知事主催のレセプションが開催された。以下では、投資プレゼンテーションの概要を紹介する。(斉藤いづみ)
ミニ・レポート
先端産業が集まるオムスク州
―シベリアの「ウラル」?―
人口約118万人、ロシア全土で第8番目の規模、2016年版「ロシアの魅力的な都市ランキング」12位につけたオムスク市を擁するオムスク州であるが、日本ではその地理的位置を含め、ほとんど知られてはいない。おそらく、ロシア市場に関わるビジネスマンにとってもあまり馴染みのない土地であると言えるであろう。本稿では、筆者が11月に実施した現地調査にて得た情報や結果をベースに、オムスク州経済の概要と現状をお伝えすることとしたい。(長谷直哉)
エネルギー産業の話題
西シベリア各地域の石油分野
西シベリアの石油分野といえば誰もがハンティ・マンシ自治管区のことを思い浮かべますが、ヤマロ・ネネツ自治管区、チュメニ州南部、トムスク州、オムスク州、ノヴォシビルスク州でも石油の生産が行われています。今回は、ハンティ・マンシでの石油の生産状況の他に、あまり注目されることのない西シベリアの他の連邦構成主体の石油分野の概要もご紹介します。(坂口泉)
ロシアと日本・出会いの風景
日本の対ロシア地域投資に関する考察
今号は、ロシアの地域がキーワードということで、日本の全都道府県を歩き渡ったロシア人として、ロシアの地域をどう見ているかという話を軽くしてみたいと思う。(D.ヴォロンツォフ)
蹴球よもやま話
サランスク・エカテリンブルグ・ヴォルゴグラード
―サッカー日本代表三都物語―
12月1日、2018年FIFAワールドカップ(W杯)ロシア大会の組み合わせ抽選会がモスクワで開催された。抽選会の結果、日本はH組に入り、グループステージの日程は次のように決まった。
6月19日 VSコロンビア@サランスク
6月25日 VSセネガル@エカテリンブルグ
6月28日 VSポーランド@ヴォルゴグラード
現地に観戦に行かれる方もおられるかもしれないし、行かないまでも、日本の試合がある街の現地事情は気になるのではないか。そこで今回は、地域特集に合わせて、サランスク、エカテリンブルグ、ヴォルゴグラードの最新事情につき語ってみたい。(服部倫卓)
ウクライナ情報交差点
ウクライナの堅調地域と不振地域
ウクライナにおいても、国内総生産(GDP)のデータを地域別に分割した地域総生産のデータが、国家統計局から定期的に発表されている。今回は、このデータを用い、ウクライナの地域別の経済動向を概観してみたい。その際に、ウクライナを西部・中部・南部・東部という4つのマクロリージョンに分け、それらの集計値を算出することを独自に試みる。(服部倫卓)
中央アジア情報バザール
トルクメニスタンの地域探訪
東京、モスクワ、ワシントン、北京・・・国の代名詞とも言えるのは各国の首都であるが、その国を理解するには首都を知るだけでは不十分と言われることは多々ある。とはいえ、いくつもある国の地方まで目を向けることは容易ではない。まして、入国しづらく、情報も限られているトルクメニスタンとなれば、首都アシガバットを見ることさえ難しいので、地域(各州)となればますます未知の世界。
ところが、トルクメニスタンの各地域には世界遺産があったり、日本と関わりが深い街があったりと、実は興味深い事実が隠されている。そこで本稿ではトルクメニスタンの地域を紹介する。
(中馬瑞貴)
調査レポート
ロシア石油ガス化学分野の今
―新プロジェクト停滞の背景―
ロシアNIS経済研究所 嘱託研究員
坂口泉
高付加価値製品の生産の強化ならびに輸入代替の促進を産業政策の最優先課題として掲げるロシア政府は、2011年にエネルギー省に命じ「2030年までのロシアのガスおよび石油化学の発展計画」という文書を策定させたが、ロシアの産業別発展計画のほとんどがそうであるように、マーケティングの裏付けが乏しい上に資金や原料基盤の確保の目処もたっていない非現実的なプロジェクトが多くを占める単なるプロジェクト・リストに類するものであることが早々に判明した。ロシアの石油ガス化学分野は従来から原料不足と資金調達の問題に慢性的に苦しめられているのだが、その現実的な解決策はそこには示されていない。その結果、安い資金と原料をめぐる新プロジェクト間の競争が激化し、少数の勝者と多数の敗者が生まれる結果となっている。その他、輸入代替の促進という国家が掲げる目標に沿い国営企業のロスネフチとガスプロムが取り組んでいる大規模プロジェクトのように、不透明な点があまりにも多いため評価をすることすら困難なプロジェクトも存在する。
本稿では、まず原料基盤の実体ならびに主要製品(複数の合成樹脂)の需給動向といったロシアの石油ガス化学分野に関する基礎的情報に言及した後に、サバイバル・ゲームの展開という現実を視野に入れながら、石油ガス化学分野の主要な新プロジェクトの現状を紹介することとする。
INSIDE RUSSIA
ようやく再出馬表明したプーチン大統領
今回から本コーナーは若干リニューアルする。これまではどちらかと言うとランダムにテーマを選んでいたが、今後は前の月のロシアのトピックを取り上げるようにしたい。また、記事の末尾に、ロシアの最新の政治経済情勢を示すデータを定型的に掲載することにする。
というわけで、本来であれば2017年11月の動きを取り上げるべきなのだが、12月に入って締め切りも過ぎた頃に大きな出来事があったので、今回は例外的にそれについて述べる。プーチン大統領が12月6日に、2018年3月18日に投票が行われる大統領選への出馬を表明したものである。(服部倫卓)
デジタルITラボ
ロシアインダストリー4.0
先日、ロシアではサイバーセキュリティやIoTなどのデジタルエコノミー分野について、2020年までに標準化が進められる、と報道された。標準化が進められるのは、次の6分野。①サイバーセキュリティ、②ビッグデータ、③IoT、④スマートマニュファクチャリング、⑤スマートシティ、⑥AI。
これは、2017年夏にプーチン大統領によって承認された「ロシアデジタルエコノミー開発プログラム」に端を発している。今回はロシアにおけるIoT分野について見ていきたいと思う。(牧野寛)
ロジスティクス・ナビ
中欧間コンテナ列車の急成長
中国の“一帯一路”政策の下で中国と欧州を結ぶコンテナ列車が急増し、その余波がシベリア鉄道にも及んでいる近況を本欄2017年11月号で紹介しました。ユーラシア鉄道網に訪れている新風を中国側から見ていきます。(辻久子)
ロシアメディア最新事情
最高学府の学部長に聞くロシアのメディア(上)
連載第2回目は、専門家の話を聞きつつ、ロシアメディアの全体的なイメージをつかんでみたいと思います。文学や政治経済といった他分野なら他にも良い大学がたくさんありますが、ことジャーナリズムに関しては、モスクワ大学ジャーナリズム学部の右に出る教育機関はない、と言われています。そこで同学部の学部長、エレーナ・ヴァルタノヴァさんにインタビューしました。ヴァルタノヴァさんは学部長になって丸10年、ご本人は北ヨーロッパ(主にフィンランド)のマスメディア研究とメディア経済の専門家です。ヴァルタノヴァさんとのやり取りを2回に分けてお送りします。(徳山あすか)
シネマ見比べ隊!!
新年に観る家族シネマ
『雪の女王』VS『スノークイーン』
年末から新年の時期、ロシアでは子供たちを夢の世界へと誘うようなバレエやミュージカル、芝居の演目が劇場にかけられ、家族でこれを楽しむ伝統がソ連時代から今も続いているようです。このたびは、日本のアニメーション界に多大な影響を与えたと言われるソ連版アニメ映画『雪の女王』(1957)、そしてロシア実写版(2015)とを見比べてみたいのです。(佐藤千登勢)
駐在員のロシア語
モスクワ案内:赤の広場編
本社や関連会社、あるいは顧客企業から初めてモスクワに出張に来られた方に、仕事の合間をみて名所旧跡を案内してあげるのも駐在員の務めである。赴任した国についてビジネスに直結する知識や人的コネクションを持つことはもちろん不可欠だが、それとともに、当地の歴史や文化への造詣があると、駐在員の「株」が上がるというものだ。(新井滋)
記者の「取写選択」
カザフで暮らす元抑留者
カザフスタンの国立劇団がこの12月、東京公演を行う。演目は「アクタス村の阿彦」。終戦後の樺太でソ連側に捕まり強制労働させられた後、カザフで定住した阿彦哲郎氏(87)の人生を描いた劇である。(小熊宏尚)









