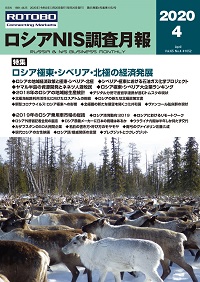 |
|
ロシアNIS調査月報2020年4月号特集◆ロシア極東・シベリア |
|
特集◆ロシア極東・シベリア・北極の経済発展 |
|
調査レポート |
ロシアの地域経済政策と極東・シベリア・北極 |
調査レポート |
シベリア・極東の石油ガス化学プロジェクト |
特別寄稿 |
ヤマル半島の資源開発とネネツ人遊牧民 ―「我々の土地」はどこに?― |
データバンク |
ロシア極東・シベリア大企業ランキング |
データバンク |
2018年のロシアの地域総生産統計 |
ミニ・レポート |
デジタル分野で産官学連携が進むトムスクの現状 |
ミニ・レポート |
北極海航路利用活性化に向けたロスアトムの挑戦 |
INSIDE RUSSIA |
ロシアの新たな北極政策文書 |
ロシア極東羅針盤 |
新型コロナウイルス:ロシア極東への影響 |
地域クローズアップ |
北極圏の新たな展望を開くコミ共和国 |
エネルギー産業の話題 |
ヴァンコール鉱床群の現状 |
ドーム・クニーギ |
田畑伸一郎・後藤正憲(編著) 『北極の人間と社会 ―持続的発展の可能性』 |
ユーラシア珍百景 |
サレハルドの「北極線」モニュメント ―2つの世界はなぜ高さが違うのか?― |
調査レポート |
2019年のロシア乗用車市場の総括 ―広がる沈滞ムード― |
ロジスティクス・ナビ |
ロシア港湾動向:2019 |
デジタルITラボ |
ロシアにおけるリモートワーク |
ロシアメディア最新事情 |
ロシア外務省記者会見の裏話 |
産業・技術トレンド |
ロシア農機メーカーに日本の商機はあるか |
ウクライナ情報交差点 |
ウクライナ内閣は半年しか持たず交代 |
中央アジア情報バザール |
カザフスタンの50大民間企業 |
ロシアと日本 ・出会いの風景 |
名前の書き方・呼び方のモヤモヤ |
ロシア音楽の世界 |
魔弓のヴァイオリン佐藤久成 ―オール・ロシア・プロ― |
シネマ見比べ隊!! |
現代ロシアの女性映画 |
駐在員のロシア語 |
姻戚関係の言葉 |
業界トピックス |
2020年1月の動き |
記者の「取写選択」 |
メドヴェージェフの憂鬱 |
調査レポート
ロシアの地域経済政策と極東・シベリア・北極
ロシア科学アカデミー情報管理研究センター 主任研究員
O.クズネツォヴァ
本稿はいくつかの章から成る。最初に、ロシアにおける地域経済政策の法的基盤がどのように変化したかを分析する。その要点は、地域経済政策の理念、すなわちその目的、課題、優先事項がどのように形成されたかということである。次に、地域発展問題を管轄する連邦権力機関にどのような変化が生じたかを考察する。続いて、極東と北極圏以外の地域政策の対象とツールの双方において生じた最も重要な新機軸について論を進め、最後に、極東、北極圏、シベリアを対象とする連邦政府の地域政策を論じる。
調査レポート
シベリア・極東の石油ガス化学プロジェクト
ロシア科学アカデミー・シベリア支部経済産業研究所
V.スースロフ・V.ギリムンジノフ
ロシアの化学産業の発展に関する従来の予測では、急速な発展の可能性は視野に入っておらず、これまでの傾向を引き継いだ慣性の法則に基づく発展が続くとの認識が示されている。しかし、化学産業のこれまでの発展のテンポは世界の平均値に近いものとなっている。これは、このままでは、世界の化学市場におけるロシアのプレゼンスに今後変化がもたらされる可能性が低いことを意味する。こうした認識を前提に本稿では、近年ロシア内外で注目されるロシア東部での石油ガス化学案件の経済性についての分析を示したい。
特別寄稿
ヤマル半島の資源開発とネネツ人遊牧民
―「我々の土地」はどこに?―
ヤマロ・ネネツ自治管区はロシア最大の天然ガス産地として知られる。近年注目を浴びている北極圏開発の一環として複数の巨大プロジェクトが進行しており、他の極北地域と比べて、この10年間に余りにも急激な変化を被った地域である。
他方で、ヤマル半島はトナカイ牧畜の一大地方でもあり、ツンドラの極北先住民による生業を中心にトナカイ飼育が営まれており、その数と規模は年々増加している。そのため、同管区は資源開発による社会的矛盾が最も激しく噴出した場所になったばかりではなく、「国家−先住民社会」の相互関係において最も劇的な展開を遂げた極北地方を体現する存在にもなった。ここで、地域の生態系と先住民族の生活様式に対して、二重の圧力を加えてきた2つの外在的要因を指摘することができる。それは、環境面の要因と経済面の要因である。(A.マゴメドフ・徳永昌弘)
データバンク
ロシア極東・シベリア大企業ランキング
小誌では折に触れてロシアの大企業ランキングをお届けしているが、今回は特集の一環として、極東連邦管区とシベリア連邦管区に絞ったランキングを掲載する。極東のランキングは以前も取り上げたことがあったが、シベリアは今回が初となる。
データバンク
2018年のロシアの地域総生産統計
ロシア連邦国家統計局は今般、2018年の同国の地域総生産の統計を発表した。地域総生産は国内総生産(GDP)を地域別に(州などのレベルに)ブレークダウンしたものだが、GDPよりも発表が遅いので、このほどようやく2018年の数字が発表されたというわけである。今号の特集「ロシア極東・シベリア・北極の経済発展」の一環として、この最新データを図表にまとめて紹介する。
ミニ・レポート
デジタル分野で産官学連携が進むトムスクの現状
シベリアには人口100万人を超える都市として、ノヴォシビルスク、クラスノヤルスク、オムスクの3つが存在する。これら都市に比べると、人口約57万人のトムスクは実際に訪問してみたところ、美しいが小ぢんまりとした都市というのが一見した印象である。産業については、ロシアビジネスに携わる方なら「原子力」とすぐに連想されることだろう。しかしながら、トムスクのビジネスにおける魅力は都市の規模に依存するものでは決してないし、また産業も原子力産業だけが有望なわけではない。本稿ではデジタル分野で産官学連携を強力に押し進めるトムスクの現状を短いながらも紹介したいと思う。(長谷直哉)
ミニ・レポート
北極海航路利用活性化に向けたロスアトムの挑戦
北極海航路の利用活性化に向け、ロシア政府は段階的に態勢づくりを行っているが、その最たる例が2018年末制定の連邦法(同12月27日)で、北極海航路での砕氷船運用、航行管理及び安全管理に関する権限をロスアトムに委任したことだろう。これに伴い、ロスアトムの所掌領域は、原子力発電所の運用や原子炉の開発、その国際展開等だけでなく、新しい分野へと大きく開かれることとなった。もちろん、北極海航路運用については、法整備面においてロシア連邦運輸省が、沿岸地域開発に関して極東・北極圏発展省が、資源開発に関してロシア国内外のエネルギー企業が関与する上、国防面でも重要な地域のため、各所との調整が欠かせない。この意味において、北極海航路の「水先案内人」としての役割を付された今般の権限委譲は、ロスアトムにとって挑戦であることは疑いがない。本稿ではこの挑戦について、ロスアトム資料を参考に、ポイントとなる事項をコンパクトに整理しておきたい。(長谷直哉)
INSIDE RUSSIA
ロシアの新たな北極政策文書
ロシアのプーチン大統領は3月5日付の大統領令で、「2035年までの北極におけるロシア連邦の国家政策の基礎」と題する政策文書を承認した。ロシアが北極を重視する動機は国家安全保障上の国益によるところが大きいと思われるが、今回の政策文書を見ると、ロシアが自国の北極圏を安定的にコントロールする上でも、その経済・社会的発展が不可欠であるという認識が読み取れる。北極政策の目的として、住民の生活の質的向上、経済発展の加速、環境保護、国際協力およびロシアの国益の擁護が挙げられている。(服部倫卓)
ロシア極東羅針盤
新型コロナウイルス:ロシア極東への影響
新型コロナウイルスの感染拡大は、中国と4,200km以上にわたって国境を接するロシア極東地域の社会と経済に大きな影響を与えつつある。現地報道をもとにまとめた。(齋藤大輔)
地域クローズアップ
北極圏の新たな展望を開くコミ共和国
コミ共和国は、多くの北極圏地域と同様に、石油や石炭、木材など、資源が豊富で、燃料エネルギー部門と林業・木材加工部門が共和国経済を支えている。気候条件の厳しい地域であるが、域内にある「コミの原生林」は世界遺産に認定されており、冠名民族であるフィン・ウゴル系コミ人の伝統的な文化の魅力を目にすることのできる「フィン・ウゴル民族文化パーク」も設置されていることから、国内で人気の観光地の1つとなっている。一方、コミ共和国では、2015年に当時の現職首長が組織犯罪を主導していた罪で逮捕され、首長の側近や地元のビジネスエリート、さらには元首長など、大勢が逮捕・起訴され大きなスキャンダルの舞台にもなった。(中馬瑞貴)
エネルギー産業の話題
ヴァンコール鉱床群の現状
ロスネフチは現在、フダイナトフ率いるネフチェガスホールディングと共同で、北極海航路経由でロシア産石油を輸出することを念頭に置いたヴォストークオイルというプロジェクトに取り組んでいます。同プロジェクトは日本でも注目されていますので、今回は、その資源基盤のひとつとして位置付けられているヴァンコール鉱床群の現状をご紹介します(その他、パイヤハという未開発鉱床も同プロジェクトの資源基盤のひとつとみなされています)。(坂口泉)
調査レポート
2019年のロシア乗用車市場の総括
―広がる沈滞ムード―
ロシアNIS経済研究所 嘱託研究員
坂口泉
ロシアの新車販売は2014年ごろから不振に陥り、2016年にはピークだった2012年の約半分の143万台にまで数字が落ち込んだ。その後、2017年春ごろから販売が緩やかに回復し始めたが、それも長くは続かず、2019年は前年比2.3%減の176万台にとどまった。わずか2%強の減少幅ではあるが、2019年も回復傾向が続くと見る向きが多かっただけに市場では動揺が広がっている。「油価の低迷ならびに石油生産量の伸び悩み傾向を受け“産油国ロシア”の経済はかつての勢いを失っており、もはや急激な数字の改善は期待できない」という見方が市場では支配的になりつつあり、攻めの経営から守りの経営へ軸足を本格的に移すメーカーやディーラーが増えつつある。特に巨額の有利子負債に苦しむディーラーたちが抱く危機感は強く、今後、市場からの退出事例が急増する可能性も十分に考えられる。
ロジスティクス・ナビ
ロシア港湾動向:2019
2019年のロシア港湾物流の主要動向を港湾統計に基づいて紹介します。加えてコンテナ貨物、ヤマルLNGと北極海航路等、注目点について解説します。(辻久子)
デジタルITラボ
ロシアにおけるリモートワーク
コロナウイルスの感染拡大が世界経済に大きな波紋を呼んでいる 中国や日本においては、通学・通勤による感染リスクを抑えるため、学校や企業が在宅学習、在宅勤務の仕組みを早急に整えている。コロナウイルスの影響で、皮肉にも2020年はリモートワークの普及が大幅に進む可能性がある。幸いにも、ロシアでは、大きなウイルス感染被害が出ていない(公式には発表されていない)が、今後の見通しは不透明であり、局地的な集団感染が発生すれば、他国と同様の措置を迫られる可能性もある。今回はロシアにおけるリモートワークの状況や、そこで使われているツールなどに焦点をあててみたい。(牧野寛)
ロシアメディア最新事情
ロシア外務省記者会見の裏話
たまには真面目な仕事の話題を、ということで、外務省の記者会見がどのように行なわれているのか書いてみます。1月17日にはラヴロフ外相の記者会見、つい先日の2月28日にはザハロヴァ報道官の会見に出たので、その様子をご紹介しましょう。(徳山あすか)
産業・技術トレンド
ロシア農機メーカーに日本の商機はあるか
最近、ロシアの農機産業が伸びているという話を聞く機会が何回かあった。同時に、ここ数年、複数のロシアの農機メーカーを訪問する機会があった。確かに、農業生産は伸びており、ロシア国産農機メーカーの生産はそれ以上に伸びている。ある一面を切り出せばロシアの農機産業が大きく成長しているように見えることもある。しかし、ロシアの農機産業の規模は限られ、品質には限界もあり、国際競争力を持った産業に育っているわけでもない。現場を見ると、ロシアの農機業界には危うさも見えるのが実情である。(渡邊光太郎)
ウクライナ情報交差点
ウクライナ内閣は半年しか持たず交代
最近のウクライナに関し注目すべきトレンドとして、経済についての楽観論が一部で語られるようになったことがある。しかし、そうした楽観論に冷や水を浴びせる動きがあった。3月4日、O.ホンチャルーク内閣が総辞職を余儀なくされたものである。2019年8月29日に35歳の若さで政府を率いることになり、世界で最も若い首相ともてはやされたのも束の間、わずか半年でその座を去ることとなり、ウクライナ憲政史上に別の意味で不名誉な記録を残すこととなった。(服部倫卓)
中央アジア情報バザール
カザフスタンの50大民間企業
「Forbes Rating Kazakhstan」が2020年2月19日にカザフスタンの50大民間企業を発表した。ここでの「民間企業」とは、カザフスタン国民が50%以上の資本を保有し、政府および外国の法人ならびに個人の保有率が50%以下の企業を指すと定義づけられている。同ランキングは各社の2018年の売上高で順位付けされているが、銀行、保険会社、投資会社といった金融系の機関は除外されている。(中馬瑞貴)
ロシアと日本・出会いの風景
名前の書き方・呼び方のモヤモヤ
日本とロシアの間にある数多い違いの一つは、人の名前の書き方と呼び方の違いだ。日本語とロシア語が言語としてあれだけ違うことから考えれば、この違いも当たり前だ。初めて人と会う時にはまず名前を名乗ったり、聞き取ったりするわけで、丁寧に対応するためにはお互いにこのあたりのニュアンスを覚えていかないといけない。名前については、おそらく多くの論文、本まで出されてあり、日本にもロシアにも様々な資料があろうかと思い、このエッセイでは何かの新たな発見をするわけではなく、いつものように個人の感想だけシェアしたい。(D.ヴォロンツォフ)
ロシア音楽の世界
魔弓のヴァイオリン佐藤久成
―オール・ロシア・プロ―
佐藤久成(ひさや)を聴いたことがあるだろうか?ヴァイオリン界の鬼才、奇才、天才、風雲児、超個性派、魔弓の使い手、魔界のヴァイオリン、孤高のヴァイオリニスト、前人未到系新種、今世紀の絶滅危惧種・・・と色んな衝撃的な紹介がされるヴァイオリニスト。私が、この5年間で最も注目して追っかけて来ているアーティストと言えば、もうすぐ白寿を迎える巨匠イヴリー・ギトリスとこの人、佐藤久成である。(ヒロ・ミヒャエル小倉)
シネマ見比べ隊!!
現代ロシアの女性映画
本コーナーでは3月8日の「国際婦人デー」に因んで、毎年、いわゆる女性映画(woman’s film)をとりあげてきました。『持参金のない娘』(エリダール・リャザーノフ監督、1984)、『モスクワは涙を信じない』(ウラジーミル・メニショフ監督、1979)、『貴族の巣』(アンドレイ・ミハルコフ=コンチャロフスキー監督、1969)、『狩場の悲劇』(エミーリ・ロチャヌー監督、1978)、『エレナの惑い』(アンドレイ・ズビャギンツェフ監督、2011)、『ヴェラの祈り』(アンドレイ・ズビャギンツェフ監督、2007)を取り上げて、時代の趨勢にも配慮しつつ、それでも一貫してあり続けるロシアの理想的女性像を確認してきたのです。今回は4月号にずれ込んでしまいましたが、やはり女性映画2作をとりあげ、ご紹介したいのです。これまでの女性映画の系譜とは異なる女性への頌歌『神聖なる一族24人の娘たち』と、現代版『モスクワは涙を信じない』と敢えて命名したい『バイ・ミー』です。(佐藤千登勢)
記者の「取写選択」
ブレグジットとウクレグジット
「クリミアはウクライナだ!」。2014年3月、キエフの独立広場では、こんなプラカードを掲げるクリミア・タタール人の集団が、ロシアのクリミア半島併合への反対を訴えていた。しかし、立ち止まって訴えに耳を傾ける市民は少ない。
行き交う人々の手には赤いバラが目立つ。ヤヌコーヴィチ政権を倒し、欧州連合(EU)との関係緊密化を目指した「ユーロマイダン革命」で命を落とした若者らへの感謝の印だ。革命の聖地となった広場を一目見ようと地方から出てきた人も目立ち、表情は明るい。ロシアがクリミアの実効支配を急ぎ、ドンバスに食指を伸ばす今は、独立ウクライナ最大の国難。革命の余韻に浸っている場合ではないはずだが―。(小熊宏尚)









